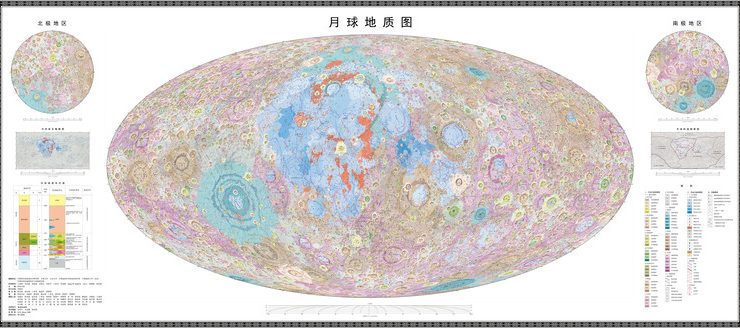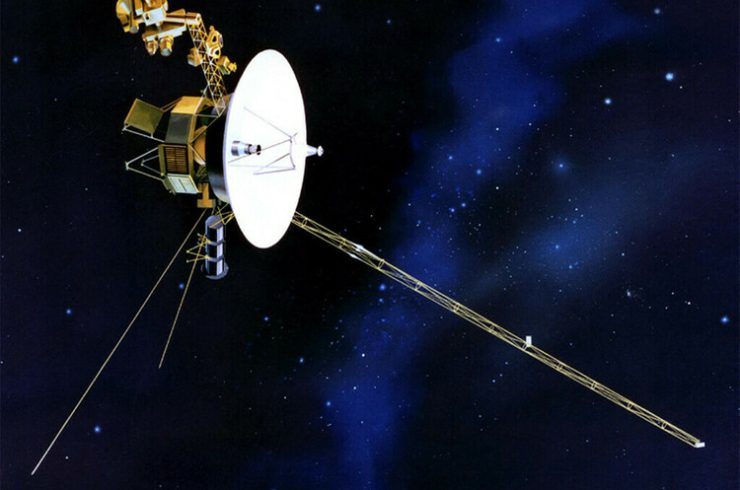坂本龍一と伊藤穰一 人工知能と人間の未来を語る

音楽家の坂本龍一氏と、株式会社デジタルガレージの共同創業者でMITメディアラボ所長でもある伊藤穰一氏は、1990年代初めから交流を続ける旧知の間柄だ。現在は、坂本氏がニューヨーク、伊藤氏がボストンと、共に米国東海岸に拠点を置き活動している。音楽、インターネットと、専門領域は異なりながらも常に最先端の技術を追いかけてきた2人が、人工知能と人間の未来について語り合った。
(英語版はこちら English version is here)
***
伊藤穰一氏(以下、伊藤):人工知能が僕らの社会に与えるインパクトは大きい。そこでMITメディアラボでは、人工知能と倫理について研究を始めている。

坂本龍一氏
坂本龍一氏(以下、坂本):個人的には、僕らが持っている「美」の意識、古代ギリシャで言うところの「真善美」を人工知能が判断できるのかに興味がある。仮にその答えが合っていたとしても、人工知能が本当にそれを認識できているのか、といったことを知りたい。つまり、ある音楽を聴いて人間が「美しい」と感じることを、人工知能も同じように理解できるのだろうか。まあそれは、人間にとっての「認識」とは何か、という問題に戻ってしまうんだけどね。
伊藤:そもそも「人間」って何なのか、というところから考える必要があると思う。アメリカでもかつては人間なのに「奴隷」として扱われていた人たちがいたわけだし、今後技術が進んで脳の機能をコンピューターがサポートするようになったら、その人は人間なのか、といった議論も巻き起こっていくと思う。2人の脳をコンピューターを介して接続し、意思を統合できるようになったら、それは人間の意思と言えるのか。そもそも、企業に「法人格」を与えているのも、人間と同様に権利を与えるためだしね。つまり、どこからが人間でどこからが機械かということはますます曖昧になっていく。結果として、どこに何の権限を持たせるべきかという倫理的な概念は、どんどん変わっていく。人間にはロボットに対して抱く特別な感情っていうのがあるんだよね。ロボットを蹴飛ばしたり、ロボットをつかんだりしていじめていると、人間はいやな気持ちになるんだ。人工知能が発展するとそのうち、一部のロボットに人権を与えることを考えないといけなくなりそうだ。
坂本:いま人間が労働者としてやっているさまざまな作業が、オートメーション化されてロボットに置きかわっていく流れは止まりそうもない。
伊藤:そこまで優秀な人工知能ができる前の段階で、人間がコンピューターに奴隷のように使われるという状況が、短期的にせよ生まれるかもしれない。コンピューターより人間の脳を使った方が安上がりになることがあるから。人間の脳が消費するエネルギーは20ワット程度。これに対してIBMの人工知能「Watson」が消費するエネルギーは50メガワットくらいと言われている。人間の体を育てるのに必要なエネルギーもかなりのものかもしれないけど、計算をしている時のランニングコストは人間の方が安いと言える。すると経済合理性を考えて、人間がコンピューターの指示に従って動く場面が増えてくる。すでに例えば画像認識では、コンピューターが処理できなかった画像の認識を人間が請け負ったりすることが珍しくない。Uberのような配車サービスだって、考えようによっては人間がコンピューターの指示に従って運転していると言える。
坂本:人間がコンピューターから仕事をもらっているんだ。

伊藤穰一氏
伊藤:MITメディアラボでは、ロボットと人間の協調について研究をしている。ペアで戦うゲームを相手が人間かロボットかわからないようにして行うと、人間同士より人間とロボットの組み合わせの方がコラボレーションできるという結果が得られた。人間同士よりもロボット同士の方が成績が良いこともある。そう考えると、人工知能は人間を置き換えるのではなく、人間を拡張するために人工知能を利用すべきと捉えた方が良い。人間と人工知能を別物として考えるのは、これからの時代を占うのに適切ではないんじゃないかな。
坂本:人工知能が普及すると、人間の働き方はどう変わるだろう。普通に考えれば、多くの人の職がなくなりそうだけど。人工知能は人間のために雇用を創出してくれるかな。
伊藤:古代ギリシャに例えると分かりやすい。アテネには奴隷制度があった。奴隷が労働を担うため、少なくとも裕福な市民にとっての「働き」は、哲学や教育、アート、社会参加などを意味した。つまり、現代社会では経済価値に換算しづらい、哲学者や研究者、アーティスト、子育てをする人の働きがアテネではすごく重要とされていた。奴隷をロボットに置き換えてみれば、これからの社会を想像できると思う。産業革命以降は「モノを作る」ことに重きをおいて社会の成熟度を定義してきたけど、「文化を作る」というのが本来の人間の脳の役割だったはず。人工知能が普及するにつれて、そちらへの回帰が進んでいくと思う。
坂本:文化を作るという方向で能力をもっと発揮しないと、人間がやることがなくなってきてしまうね。僕も人工知能の利用については基本的にポジティブなので、人工知能が作曲することは構わないし、出来上がった音楽が面白かったら評価はするでしょう。でも、その音楽がどういうプロセスで、どのようなプログラムによって作られたかの方が大切だと思う。モーツァルトの曲を人工知能に全部覚えさせて、統計的に似たような曲を作るのは簡単にできるじゃない。それでは面白くないよね。少なくともその音楽の美の本質が何なのかというのをアルゴリズム化しないと。まあ、それに意味があるかどうかは別だけど。人工知能は、人間が思いつかない、人間には絶対不可能な量の計算が得意なので、そこから何が生まれるかに期待したい。出来上がった音楽を僕らが聴いて面白いと思えば、それは恩恵だと思う。
伊藤:このまま技術が進むと、宇宙の全てをコンピューターで再現し理解できる、「シンギュラリティー」が実現すると信じている人たちがいる。彼らは世界の複雑さやコンピューターの性能あまりにも単純に捉えすぎていると個人的に思う。世の中の複雑さをコンピューターの力だけを頼って解き明かそうとしていて、精神世界に触れた経験の少ない起業家やエンジニアにこうした傾向があると感じる。最先端の科学を信じきってしまうと、社会を間違った方向に導くリスクが高くなる。優生学運動が盛んだった頃、進化と遺伝について理解したと信じきって、「劣っている」とみなした人に不妊治療を行ったり殺したりしたりすることが、社会にとって良いことだと思う人たちがいたように。人工知能にしても、バイオにしても、技術を完全に理解できたと信じ込んだ人々が社会の中で権力を持つようになることを僕は恐れている。本来科学というものは、畏敬の念を持って謙虚に愛さないといけないものなのに、こうした人々はその謙虚さを失っている。
坂本:そこは、日本的な文化とか感性が重要になる部分だと思う。日本列島はアジアの端っこで周りは全部海。だから東西南北いろいろな方向から人や文化が押し寄せてきて、何千年、何万年といった長い時間をかけて集積した非常に多様性に富んだ場所だと思っている。こうした中で、独特な歴史や文化が育ってきた。僕は音楽家だから音楽を例にすると、能など日本の伝統芸能の起源は、中国の民衆音楽である「田楽」で、これが日本に伝わって日本の仏教と混じり合って洗練された形になり、世界にない非常にユニークなものになった。輸入したものを非常に長く残し、面白い文化を形作っていくというのが日本の歴史で繰り返されてきた。神道も日本独特のものだけど、その本質はアニミズムというユニバーサルな感覚にある。アニミズム自体は例えばヨーロッパにもあったが、今はほとんど消えてしまった。ところが、日本には色濃く残って、それがベースとなり神道ができている。だから、自然と対立的に生きていくのではなく、自然と融和し共生していくための技術とか感覚、感性に長けているの思う。
伊藤:例えば、伊勢神宮が20年ごとに建て替えることを1000年以上も続けてきたように、日本ではなんでもサイクルで考えるという文化が染み込んでいる。これに対してアメリカの文化は、経済的に永遠に伸び続けないとハッピーじゃないという考え方に基づいている部分が多い。こうした考え方に固執すると、環境も破壊されるし、お金を持っている人と持っていない人の差が広がると言った具合に、社会のいろんなシステムが壊れてしまう。
坂本:今の勢いで成長を求めていけば、無限に成長なんてできるわけないので、どこかで必ず揺り戻しが起こる。それが自然環境に破壊的な結果を引き起こす可能性がある。だからうまいところで、成長ばかりを求める動きを色褪せさせるために、経済のあり方も大きく変わらないといけないと思う。
伊藤:この前、日本の中学生と話をする機会があったので「環境の話をしよう」と水を向けた。するとひとりが「環境って人間が入っている環境?それともいなくていい環境?人間は決して環境にいい存在ではないよね」って質問してきた。すると別の子が「そもそも自分たちの人生の意味をもっと考えてから議論した方がいいんじゃない」と言った。大人と話をするとすぐ「カーボン排出量が…」みたいにしたり顔で話をするけれど、「自然には人間が必要なのか」というそもそも論を中学生たちが考えていることって、これからの文化を作る上ですごく希望が持てることだと思った。
坂本:こういう感覚を持った子供たちがそのまま育っていくような仕組みを作ってあげたいね。
(構成:枝 洋樹)