基礎研究、生産開発期間を1/4以下に 酵素利用にイノベーションを起こすdigzymeの挑戦

独自の酵素開発技術を開発・提供する株式会社digzyme(ディグザイム)代表取締役CEOの渡来直生氏
突然だが、皆さんは「酵素」というものをご存じだろうか。酵素とは、簡単に言うと「タンパク質の一種で、さまざまな化学反応を促す物質(触媒)」だ。
例えば、ご飯を噛み続けると、唾液がたくさん出て、甘みを増してくる。これは、唾液に含まれる酵素(アミラーゼ)が、炭水化物(でんぷん)を分解して、甘い糖にするために起こるものだ。このように、植物や動物の体内でもたくさんの種類の酵素が働いており、生きていくために必要な消化や吸収、代謝などの化学反応を促している。
実はこの酵素は、食品・化学・洗濯用洗剤・繊維・バイオマスエネルギー・飼料・農業・医療など非常に多くの分野で利用されている。例えば、おいしい食感を生み出す酵素、衣服の汚れを落とす酵素、廃棄物を分解する酵素など、さまざまな機能を持つ酵素が開発され、プロダクト作りに活用されている。
さまざまな分野で産業利用されている酵素だが、その利用目的に合った新たな酵素を開発することは非常に難しい。まず、膨大な種類の中から、目的に沿った特性を持つ酵素を見つけなければならず、気が遠くなるようなトライアンドエラーが必要となる。さらに、運良く目的に合う酵素を見つけたとしても、今度はそれを産業利用しやすいように改良しなければならない。こちらも試行錯誤を繰り返すことになり、時間も手間もかかる。このように偶然に頼る要素が大きいため、酵素を活用した新規プロダクトの開発には、5年〜10年もの時間がかかるケースが少なくないのだ。
こうした酵素活用の課題に着目し、酵素の探求や改良にかかる時間を大幅に短縮するソリューションを開発・提供するスタートアップがある。それが、バイオインフォマティクス(情報生命科学)に基づいた酵素開発技術を持つ東京工業大学発のスタートアップ、株式会社digzyme(ディグザイム、本社 東京都港区、2019年創業)だ。
創業の経緯やソリューションの強みについて、代表取締役CEOの渡来直生(わたらい・なおき)氏に聞いた。
ルーツは“アカデミア”にあり
digzymeは、渡来氏が東京工業大学の博士課程3年のときに立ち上げたバイオスタートアップだ。当時、渡来氏は、生命科学と情報科学を融合したバイオインフォマティクス分野を専門とする研究室に所属していたが、その研究テーマのひとつに「酵素探索」があったという。
酵素探索とは、主に植物が作るさまざまな物質が、どのような酵素をもとに作られているかを解き明かす学問領域だ。渡来氏が所属していた研究室では、酵素の探求とともに、その研究データを蓄積していくオープンデータベースの整理・構築にも尽力していた。
「このデータベースをうまく整理、解析するための技術を作ることが、我々の研究テーマのひとつでしたが、ある企業との共同研究をした際に、我々が普段使っている技術やツールを応用することで、(企業の)目的の沿った酵素を効率よく見つけ出せることがわかりました。これが当社を設立するに至った最初のきっかけです」(渡来氏)
この経験をふまえて、おそらく産業界には同様の課題があるだろうと、渡来氏が企業のニーズに応えられることを広く紹介していくと、求めている企業がたくさんあることがわかったという。
「そんな中で、私が博士課程3年のときに、新たに企業との共同研究が立ち上がることになったので、急いで会社を立ち上げ、そこで(共同研究を)受けることにしたのです。これがdigzyme立ち上げの経緯です」
基礎研究を1/4以下にまで短縮
現在、digzymeでは、「digzyme Moonlight™」と「digzyme Spotlight™」という2つの情報解析プラットフォームを提供しているほか、2024年4月からは、総額7.3億円の調達資金(シリーズA)をもとに、高機能な酵素のライブラリ「digzyme Designed Library™」の構築も進めている。
それぞれどういうものかと尋ねると、渡来氏はまず「digzyme Moonlight™」について、「求める特性を持つ酵素を、データベースからスクリーニング(絞り込む)してくれる」ものだと説明してくれた。
冒頭でお伝えしたように、酵素を活用したプロダクトを開発する際には、まず膨大な酵素群の中から、目的に沿った特性を持つ酵素を見つけ出す必要がある。その際、従来の手法では「ランダムに何度も、“当たりくじ”が出るまで、実験を繰り返すことしかできなかった」という。
「『digzyme Moonlight™』は、この“当たりくじ”が大体この辺にあるよね、と探す範囲を絞り込んでくれます。実験を数回繰り返せば、求める酵素が見つかるぐらいにまで絞り込んでくれるので、酵素の探索プロセスを大幅に短縮することができます」
もうひとつの情報解析プラットフォーム「digzyme Spotlight™」は、求める特性を持つ酵素を見つけた後「その特性を改良する際に活用できる」ものだという。
「digzyme Moonlight™」を開発した当初、渡来氏らは、膨大な酵素のデータベースから、求める酵素を見つけるだけで企業側のニーズは満たせると考えていた。しかし、見つけた酵素をそのまま事業活用できるかというと、そうではなかった。酵素の能力が足りなかったり、製造プロセスにうまく合わせられなかったりすることが頻繁に起こり、酵素の機能改良をサポートする必要性を感じたという。そこで開発したのが「digzyme Spotlight™」だ。
「酵素の機能改良には、昔からよく用いられている手法として、『改変』というものがあります。これは、酵素の遺伝子の一部を変えることで機能改良する手法ですが、その改変の方法(遺伝子を変化する箇所)を効率的に探し出してくれるのが『digzyme Spotlight™』です」
アカデミアの世界には、すでに改変に関する膨大なオープンデータベースが存在する。渡来氏らは、そこからデータを集め、分析してくれるAIを開発。そのAIの情報をもとに、求める機能改良を実現するための改変の方法を示してくれるのが「digzyme Spotlight™」というわけだ。
「この2つの情報解析プラットフォームを活用することで、これまで数年かかっていた(酵素を活用したプロダクト開発における)基礎研究の期間を、少なくとも、従来の1/4以下にまで短縮できるようになりました」
酵素ライブラリも構築中
では、現在構築している「digzyme Designed Library™」とは、どのようなものか。渡来氏は「ここまで触れた2つの解析プラットフォームとは全くの別物」で、「digzyme Designed Library™」を構築するとは、すなわち「酵素のライブラリを作ること」だと説明する。
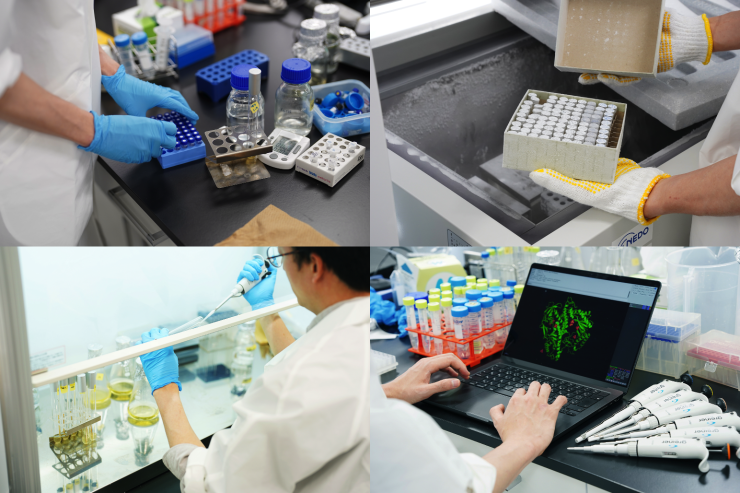
渡来氏らが提供する2つの情報解析プラットフォームは、すでに複数企業の利用が進んでいる。そうした企業で渡来氏らが主にコミュニケーションする相手は、「研究開発部門の人たち」だ。研究開発段階においては、先方が必要とする酵素がどのようなものなのかを共有しながら仕事を進めればよいが、その先の「生産寄りの部署の人たち」とは、実際のモノ(酵素)がないと、なかなか話が前に進まないという。
「現状でも、企業の基礎研究に携わる人とはニーズベースの話ができますが、やはり、その先の部署の人たちのことを考えると、我々がちゃんと酵素を保有し、提供できる能力がないと、話が前に進みません。この課題を解決するため、今回調達した資金をもとに、産業的に有用なパラメーターを持つ酵素をどんどん作り、ライブラリを構築することにしたのです」
現在、渡来氏らは、東京都江戸川区葛西のラボ内で、さまざまな種類の酵素を作る微生物株を培養しており、今年(2024年)の秋頃には、ライブラリとしてサービスを提供できるようになるだろうとのことだ。この「digzyme Designed Library™」が完成すると、企業が求める酵素のサンプルを、例えば一週間で提供するなど、スピーディに製品開発を進めるための環境が整う。
「『digzyme Designed Library™』が機能するようになると、これまでの基礎研究に加え、生産開発の期間についても、従来の1/4以下にまで短縮できるようになると考えています。酵素を活用したプロダクト開発を、これまで以上にサポートができるようになります」
幅広い分野でイノベーションを
競合他社に対する強みを聞くと、渡来氏は「酵素に特化していること」を挙げた。酵素をビジネスの一部として扱っている企業は他にもあるものの「酵素に特化して、(プロダクト開発の)基礎研究から生産開発まで全て携わっているのは、おそらく当社だけ」とのことだ。
最後に今後の展望を尋ねると「幅広い分野でイノベーションを起こしたい」との答えが返ってきた。現在digzymeでは、食品系企業とのビジネスは広がってきているものの、環境分野やライフサイエンスなどの研究分野においても、酵素を活用できる領域は広く、その開発にも携わりたいと考えているという。
例えば、環境分野であれば、これまでうまく分解できずにバイオマスとして活用できなかったゴミも、酵素をうまく活用すればエネルギー源として変換できる。研究分野においても、酵素を活用し、研究の期間短縮やコストダウンに貢献できる研究用試薬を生み出せる可能性が高いという。
「環境や研究分野における酵素の活用は、社会にとっても有益なものだと思います。将来的にはこういった分野にも広く参入し、イノベーションを起こしたいと考えています」(渡来氏)
酵素を活用したプロダクト開発は、生物由来の物質を用いるため、環境負荷も少ないと言われている。digzymeの活動が社会に広く浸透し、環境負荷低減につながることも期待したい。












