生成AIがビジネスに与える影響を、AIの専門家はどう捉えているのか
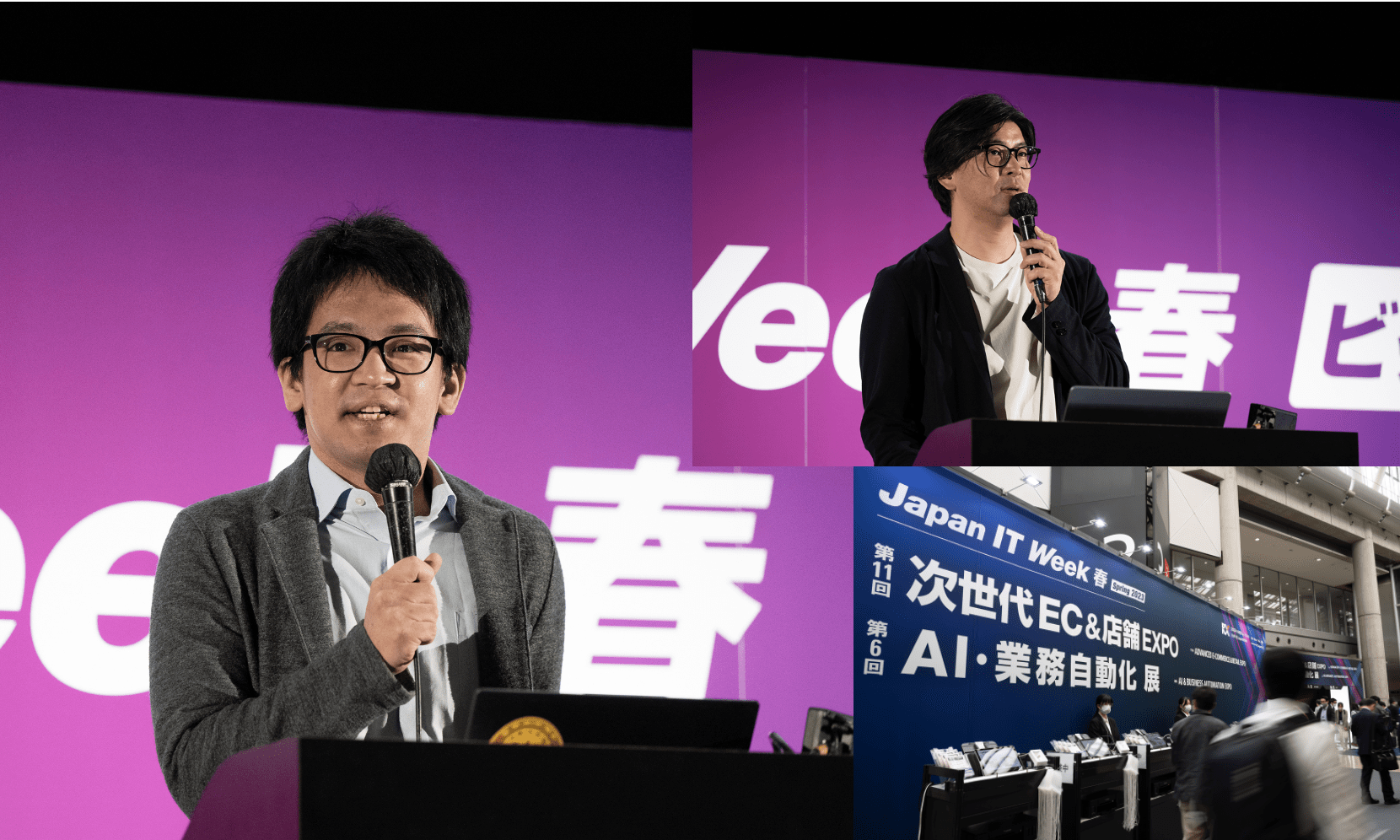
東京ビッグサイトで開催された「第32回Japan IT Week春」の様子
文章や画像などさまざまなコンテンツを生成できる生成AI(Generative AI)が、今大きな注目を集めている。特に、米国のOpenAIが開発した対話型生成AI「ChatGPT」については、その利便性の高さから、さまざまな活用法が模索される一方、社会への影響の大きさを懸念する声も多方面からあがっている。
こうした生成AIに対し、AI開発の現場ではどういった動きが出はじめているのか。また、ビジネスへの影響はどういったものが考えられるのだろう。
2023年4月5日〜7日、東京ビッグサイト(東京都江東区)にて、「第32回Japan IT Week春」が開催された。その中で、東京大学松尾研究室発のAIスタートアップである株式会社ELYZA(東京都文京区)の取締役CMO・野口竜司氏が登壇し、『シンギュラリティは近い?次世代AIの今とこれから』と題した講演を。株式会社エクサウィザーズ(東京都港区)取締役の大植択真氏が『AI活用を変える2023年3つの潮流、対話/生成AI・ノーコード・Web3』と題した講演を行った。
シンギュラリティは起こるのか?
講演の冒頭で野口氏は、そもそも生成AIとは何なのかを解説した。AIには、機械学習という特定のタスクを実現するための手法があり、その中には人間の脳の神経細胞を模倣したディープラーニングがある。生成AIは、このディープラーニングによって実現したもので、「言語AI」と「創るAI」の2系統に分かれているという。
「言語AI」と「創るAI」は、どちらも発展がめざましく、例えば「創るAI」のひとつであるMidjourneyが生成した画像などは、「ちょっと感動するレベル」にまで達していると野口氏は評価する。
一方「言語AI」ついては、代表的なものとしてChatGPTを挙げ、その進化状況を以下のように説明する。
「ChatGPTは、『大規模言語AI』と呼ばれたりしますが、(ここ数年で)とにかく巨大化しました。巨大化することで、2年前にはできなかったこと、例えば、『ゼロから文章を生成』したり、『流暢で自然な対話』をしたり、『意味や意図の理解』や『知識を元にした対話』といったことも得意になりました。日本の医療系の試験も突破するなど、高度な専門知識を持っていないと解けないようなお題もこなせる状態になっています」(野口氏)
さらに、こうした生成AIのめざましい進化に伴い、米国のレイ・カーツワイル氏が提唱する「シンギュラリティ(技術的特異点)」が起こる可能性が非常に高まっていると、野口氏は持論を展開する。
まず、シンギュラリティまでの道のりを示す「シンギュラリティタイムライン」では、「2045年に“すべての人間を合わせた脳力”をAIが超える」とされている。そして今年(2023年)に関しては、「AIが“一人”の教育を受けた人間と同等の知性になる」と予測されていた。これが「ものの見事に言い当てている」(野口氏)。
「さらに(生成AI開発に対する)規制がなければ、2045年を待たずして、再来年あたりに、ほぼ全ての人間を合わせた“脳力”を、AIが超えてしまうといったことが起こり得ると言った方がよさそうです」(野口氏)
“専用データベース開発競争”が起こる?
続いて登壇した大植氏は、ChatGPTをはじめとする対話型生成AIは、突然現れたものではなく、「10年前からの技術進化の結果」であると説明した。
まず、2012年のディープラーニングの登場により、AIの画像認識技術などが高度化された。その後2017年にGoogleが発表した深層学習モデルのTransformerにより自然言語処理能力が飛躍的に高まった。遠くの単語間の関係性も保持できるようになり、パラメータ数を増やせば増やすほど精度が向上することもわかったという。こうした研究の中で、モデルのパラメータや学習データの数を増やした大規模基盤モデルが作成され、2022年の、多彩な対話型の生成AIの登場につながったとのことだ。
「実はこれまでのいろいろな研究や開発があり、今に至っているということです」(大植氏)
では生成AIの登場により、AI開発やビジネスの現場はどのような影響を受けるのだろう。
大植氏は、特に注目すべきキーワードのひとつとして、「LangChain」を挙げる。LangChainとは、簡単にいうと、ChatGPTなどの大規模言語モデルを使ったサービス開発を支援するライブラリのことだ。
例えば(現時点の)ChatGPT単体では、学習時点のデータにもとづく回答しかできないが、ここにLangChainが加わると、AIがGoogleで情報を検索したり、専用データベースを検索したりして、最新情報を踏まえた回答をするようになる。つまり、これまで人間が行っていたリサーチ業務などを「AIがコンピューター上で全て再現できるようになる」可能性が極めて高いという。
さらに、こうした状況を受け、今後は、AIに専門的知識を学習させるための「業界専用のデータベースの開発競争」が業界ごとに起こるだろうと大植氏は予測しており、現実にその兆しが現れている。
例えば、気象のデータベースを開発し、AIに学習させることで、天気に関するより精緻な情報を提供してくれる生成AIを開発できるようになる。あるいは、裁判の判例データのデータベースを開発し、AIに学習させることで、法務向けの生成AIを作成することもできる。
こうした各々の業界ごとに専門データベースをいち早く作ることが、生成AIの最大活用につながり、ひいては企業の競争力向上につながるというわけだ。
では、生成AIの登場でビジネスの現場はどう変わるのだろう。大植氏は、「(顧客データを活用した価値創造モデルの)本質は変わらないだろう」と分析する。
AIを活用する以前の顧客データの活用モデルは、従業員が手動でデータを集めてきて、それを分析し、サービスに反映するというものだった。これが、AIの発展により大きく変わった。
まず、顧客データが自動で貯まっていくため、AIの分析能力などが向上し、サービスの品質もあがっていく。さらにこれより、ユーザー(顧客)が増え、その結果、データの蓄積がさらに進み、AIのさらなる能力改善につながる。
「企業にすると、この“AIぐるぐるモデル”をいかに自社で回せるか、いかにユニークなデータを獲得するかがポイントになります。そして、これ(サイクル)が生成AIによって、さらに加速したということかなと、私は捉えています」(大植氏)
ちなみに、OpenAI CEOのサム・アルトマン氏も同様の発言をしており、顧客データ活用の循環を加速した企業の中からは、「Google並みに大きくなるビジネスも出てくると思う」とコメントしているとのことだ。
この他にも大植氏は、今後ビジネスパーソンには「データサイエンスの基礎的理解」に加え、AIに「問いを立てる力(プロンプト)」が強く求められるようになる他、特にホワイトカラーのミドルマネジメント(中間管理職)が大きく影響を受けるとし、将来的には「戦略的な意思決定を的確に行いながら現場の自主性を尊重する経営レイヤーか、部下を鼓舞して成長を促しながら現場の第一線で事業を押し進める現場リーダーかの二極化が進むだろう」との見解も示した。
今後社会に大きな影響を与えることになるだろう生成AI。各人が、向き合い方を熟考すべき段階に入ったと言えそうだ。











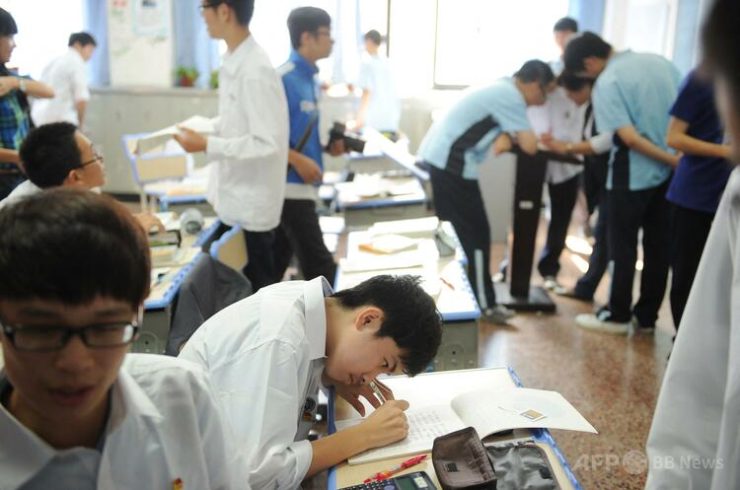

 スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs
スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs