宇宙開発におけるベンチャーの強みは?〜「第5回宇宙シンポジウム」講演より

東京理科大学 スペースシステム創造研究センター主催「第5回宇宙シンポジウム」におけるパネルディスカッションの様子
宇宙においても、スタートアップが果たす役割が大きくなっている。スタートアップ向け補助金制度「SBIR(Small/Startup Business Innovation Research)」(文科省)でも、宇宙分野に556億円の予算が割り当てられている。
一般にスタートアップやベンチャーの強みは、意思決定の速さやリスクテイクができること、柔軟なピボット(事業転換)などが挙げられるが、宇宙分野においてもこうした特性は強みとなるのだろうか。
2024年3月22日、東京理科大学神楽坂キャンパス(東京都新宿区)にて、東京理科大学 スペースシステム創造研究センターが主催する「第5回宇宙シンポジウム」が開催された。その中で「宇宙開発の商業化におけるベンチャーの役割と期待」と題したパネルディスカッションが行われ、宇宙分野におけるスタートアップやベンチャーの強みや固有技術などについて議論が交わされた。
登壇したのは、SBIRにも採択されている5社の代表だ。まず北海道大樹町の北海道スペースポートでロケット開発に挑むインターステラテクノロジズ株式会社の稲川貴大氏と、有翼ロケットを開発する株式会社SPACE WALKERの眞鍋顕秀氏、宇宙における輸送システムの実現を目指す将来宇宙輸送システム株式会社の畑田康二郎氏。そして、自社開発した「水エンジン」を用いてデブリ削減に挑む株式会社Pale Blueの中川悠一氏、「スペースデブリ化防止装置」を開発する株式会社BULLの宇藤恭士氏だ。モデレーターは、東京理科大学 創域理工学部 機械航空宇宙工学科の米本浩一教授が務めた。
先行する米国の強み 整いつつある日本
最初のテーマとなったのが、宇宙開発における「ベンチャーの強み」だ。まず稲川氏が口火を切り、米国におけるベンチャーを取り巻く状況から説明した。
ここ10数年で米国では、「民間側の勢いが昔に比べてケタ違いに増し、その中でベンチャー企業が非常に重要な位置を占めるようになった」と稲川氏はいう。特に宇宙輸送の分野では、ロケットベンチャーが20社、30社と登場し、これらが統廃合される中で、スペースX(SpaceX)などの有力企業が生き残っている状況だとした。
さらに、こうした中で「研究はされたが、採用されなかった技術」が大量に溜まってきたことが重要であり、これらを巧く組み合わせ事業化しているのが「現在の“イケてるベンチャー”」だと述べた。
「例えばスペースXは、ロケットが打ち上がって戻ってくるところばかりが注目されますが、実は彼らが低コストを実現できるポイントは、ロケットエンジンにあります。このロケットエンジンは、米国の中ではフラッグシップ(最上位)のものではなく、2番手、3番手で採用されなかった、低コストエンジンの研究開発を巧く事業にのせたもの。これがスペースXの強みになっているのです」(稲川氏)
インターステラテクノロジズも、まさにこうした「研究はされたが、採用されなかった技術」であるメタンエンジンの開発に注力しており、国内に眠っているアセットを活かすことで自社の強みにつなげているとのことだ。

さらに、経産省でスタートアップ支援を担当した経験を持つ畑田氏によると、スタートアップやベンチャーが「リスクが高い技術や事業に賭ける」ことを促す“投資家側の事情”も大きな影響を与えていると説明する。
例えば米国では、10兆円、20兆円ものベンチャー投資が行われているが、この巨額の投資の裏には、「大口の法人投資家である機関投資家などが、ベンチャー投資に一定のポートフォリオを置いていること」があるという。
「これはなぜか。(機関投資家が)年金基金などのお金を運用して、パフォーマンスを上げていこうとすると、安定資産だけに張っていては、出資者にリターンできないという危機感があります。そこで一定の利率で、リスクは高いがリターンも大きいベンチャー企業に投資して、お金を増やしていく必要があるのです。そういう運用者側のニーズから、ベンチャーはとにかくリスクが高いところに、一か八か賭けて、思い切りフルスイングしてくれと。そういう働きかけが盛んに行われているのです」(畑田氏)
さらに日本でもこうした投資の「質や量」が整いつつあり、宇宙スタートアップやベンチャーの思い切ったリスクテイクを後押ししているとした。
Pale Blueの中川氏は、従来10年ほどかけていたロケットや人工衛星の開発スパンが、近年では1年、2年ほどにまで短縮されており、「こうした従来ではありえないスピード感の中で、バリュー(価値)を発揮しやすいのがベンチャーだ」と分析する。
「宇宙産業の金銭的なハードル、時間的なハードルがグッと下がったことによって、スピード感があって、リスクを取れる人が勝ち筋を見出せる世界になってきた。これが、ベンチャーが強みを発揮できるようになった大きな理由だと思います」(中川氏)
「技術」と「宇宙」についての各社の見解
宇宙スタートアップやベンチャーが、国内外の企業と競争していくうえで、大きなポイントとなるのが技術力だろう。パネルディスカッションの後半では、各社の「固有技術」についても議論が及んだ。
まず稲川氏が、「(工場を持たない)ファブレス企業が増える中、(インターステラテクノロジズは)自社に工場を構え、ものづくり的な要素が強いところにキモがある」と切り出した。現在、自動車メーカーと連携して技術者を迎え、ものづくり現場の改善を行うことで、低コスト化を図っているという。
「ロケットや宇宙機のものづくりは、改善の余地がものすごくあります。というのも、日本の宇宙開発のサイクルはまだそんなに回っておらず、作った数も、試行錯誤の回数も少ない」(稲川氏)
こうした宇宙分野のものづくりの現場に、自動車産業で培われた低コスト化の知見やノウハウを適用していくことで「劇的にコストが変わる」とし、ものづくり重視の姿勢に勝ち筋を見出していると述べた。
この意見に強く同意したのが、Pale Blueの中川氏だ。中川氏は、自身が約10年「水エンジン」の研究に携わった経験から、固有技術には「絶対の自信がある」と強調。その一方で、自分たちが持っているのは「(水の)推進機の技術であって、推進機を具現化する技術ではない」とし、現時点では「ものづくりの技術が足りない」とも述べた。
「ものの具現化には、ほんとにいろんな苦労が詰まっていて、日本のこれまでの企業さんは、これをずっとやられてきたのだなと実感しているところです。稲川さんの言われた自動車業界もそうですし、特に我々は、医療業界など、あまり数は出ないが高付加価値の商品を作ることを、民生でやられていた方の技術をどんどん取り入れないといけないと思っています。これをきっちり実現していくことで、真に国際市場で戦える技術になると考えています」(中川氏)
ものづくりを重視する意見が出る一方で、そもそも「優位性のある固有技術」がいまだ確立していないのが宇宙開発の世界であり、(ものづくり以前に)柔軟に各社の技術の良いところを取り入れる姿勢が大事だとする意見も飛び出した。
眞鍋氏が代表を務めるSPACE WALKERは、東京理科大学発の“技術ありき”で誕生したベンチャーではあるものの、同社が開発する有翼ロケットは、「形もシステムも全然決まっておらず、そもそもどういうものが最適な宇宙エコシステムなのかも、まだゼロイチの段階」だと説明する。
このフェイズだと、「材料を何にするのか、そもそもオートパイロット(自動運転)がいいのか、有人機がいいのかなど議論が尽きない状態」であり、「絶対的に優位性のある固有技術というものは、まだない」という。
「そう考えたときに、我々が研究開発している技術以外のものが対応できるかもしれないので、そういう世界の革新技術を常にリサーチしながら、別のものを取り入れることも、やはりベンチャー的な戦い方だと思いますし、国際市場で戦えるやり方だと思います」(眞鍋氏)
ここで注目を集めたのが、「スペシャルな技術を持つという発想からの脱却を模索している」と述べたBULLの宇藤氏の発言だ。
宇藤氏は、「固有技術よりも、“技術の固有化”が今後必要になる」との見解を示す。
「変な言い方ですが、“大したことがないと言われる技術”をいかに活用するかに限るのかなと。これは技術をリスペクトしていないというのではなく、技術はあくまで手段だという考えに則った発想です。そう考えたときに、宇宙で使う技術と、地上で使う技術で何が違うかというと、『(使う場所が)宇宙であるかないか』だと極論、思っています。すると、試行錯誤の回数が圧倒的に多い地上の技術を使わない方がおかしい。逆にいうと、宇宙は特別だという考え方をいかに外すかが、これからの課題だと思っています」(宇藤氏)
宇宙スタートアップやベンチャーの取り組みは多種多様であり、固有技術に対する考え方もさまざまのようだ。各社の切磋琢磨の中から、今後の宇宙開発を牽引するような技術や事業が生まれるのだろう。各社の今後の取り組みとその成果に期待したい。





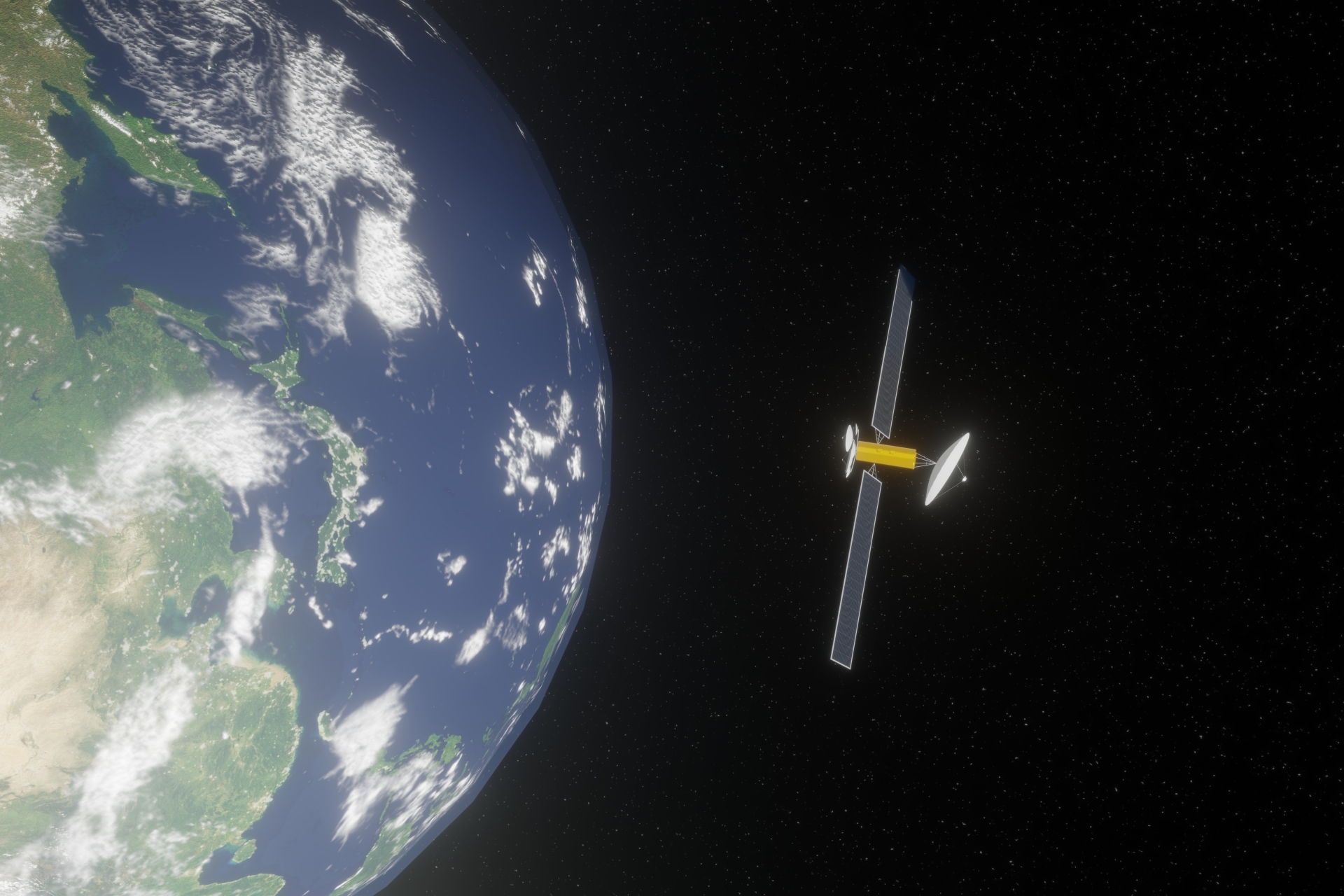









 ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり
ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり