AI活用のルールづくり この先企業に求められるのは?「JDLA Connect 2025 〜AI戦略とガバナンス〜」講演より

一般社団法人日本ディープラーニング協会開催「JDLA Connect 2025〜AI戦略とガバナンス〜」の様子
生成AIがビジネス現場にも大きな変革をもたらしている。しかし、AIの用途が広がり活用が進むにつれて、新たな課題も増えてきた。こうした状況下でAIの利用を進めるにあたって、日本や海外ではどのような議論が進んでいるのだろうか。
2025年3月26日、AKIHABARA UDXギャラリー(東京都千代田区)にて、一般社団法人日本ディープラーニング協会(JDLA)による「JDLA Connect 2025〜AI戦略とガバナンス〜」が開催された。その中で「AI戦略とガバナンス」と題した講演が行われ、ルールメイキングの国際動向やAI戦略など最前線の知見が共有された。
登壇したのは、東京大学大学院工学系研究科教授でJDLA理事長の松尾豊氏と、東京大学 東京カレッジ准教授でJDLA理事の江間有沙氏、株式会社ABEJA代表取締役CEOでJDLA理事の岡田陽介氏、株式会社zero to one代表取締役CEOでJDLA理事の竹川隆司氏の4名。モデレーターは経済キャスターの瀧口友里奈氏が務めた。
「イノベーション促進」と「リスク対応」は両立
冒頭、松尾氏がAI開発の最新動向や日本政府の動きを紹介した。
松尾氏はまず、中国のスタートアップが開発した「DeepSeek」の登場がNVIDIAの株価下落を引き起こすなど大きな反響を呼んでいるほか、OpenAIの「Deep Research」や中国Monica社のAIエージェント「Manus」の登場により、AIが自律的に市場調査や分析レポートを作成できるようになったことに触れた。
さらに、米国のPhysical Intelligenceが汎用ロボット基盤「π0(パイゼロ)」を発表し、ロボットが人間の指示に基づいて洗濯物をたたむ・テーブルを片付けるなどの一連のタスクを行えることが示され、AIの活用範囲が“物理空間”にまで広がりつつあることも付け加えた。
このように技術の進化が加速する中で「当然AIに関するリスクについても議論されている」と日本政府の動向にも言及する。
松尾氏によると、2023年5月には内閣府に松尾氏が座長を務める「AI戦略会議」が結成され、2024年8月にはその中にAIの法律や制度について議論する「AI制度研究会」が立ち上がり、同年12月に「中間取りまとめ」が提出された。
講演内で紹介された「中間取りまとめ」の主な内容は以下の通りだ。
まずAIリスクへの対応に関しては「今あるものだけでなく、技術の進化に伴い新たなリスクが立ち上がること」を前提に「技術の進化に応じて適切に動けるよう政府が司令塔の機能を持ち、 ある程度“調査する力”を持つべき」だということ。
AIの法律に関しては、たとえば犯罪者が生成AIを用いて詐欺をしたとしても、その犯罪行為自体は現行法で裁けることから、「(AI活用そのものを取り締まるのではなく)必要に応じて現行法をきちんと適用していくことを重視すべき」であり、そのためにも「AI事業者がある程度の透明性・安全性に配慮する必要がある」ことが示されたという。
これらの提言を受け石破総理は、2025年2月末に「AI法案」を策定することを閣議決定している。
「政府は基本的には『AIによるイノベーション促進』と『リスクの対応』をトレードオフではなく“両立する”としています。日本の場合は特に『リスク対応をしないとみんな怖がってやらない』ということが多々ありますので、『どこまでやっていいのか・悪いのか』を明示しながら、それによってイノベーションを促進するとしています」(松尾氏)
「強気の受け身」から「ルールメイカー」側へ
では国際的なルールづくりはどの方向に向かっているのか。セッションの中盤では、江間氏がルールメイキングの国際動向を「ここ10年の歴史」を紐解きながら解説した。
江間氏はAIに関するガバナンスや法律についての議論は2016年頃から始まっており、日本でも総務省などが中心となり「国際ルールメイキングに貢献してきた」と切り出す。
「国際的にも日本国内においても2016年ぐらいから、AIの利用に関して(長期的な視点も含めて)これからAIが良くない使われ方をしたときに、どのような指針で考えればいいのかという議論が行われました」(江間氏)
議論されたのは、AI利用に際して「プライバシーやセキュリティをどう守るのか」。あるいは「データによってAIにバイアスが生じて何か問題が起きないか」「誤作動が起きたときに不都合はないか」「誤情報、偽情報を拡散してしまわないか」といった、今日まで議論されて続けている論点が俎上に上ったという。その後2018年頃には、AIの公平性や安全性、透明性を含め「開発する企業がしっかりと考えていくことが大事だ」という原則が固まり始めたのこと。
「日本を含めたG7、G20、OECD(経済協力開発機構)などでいろんな原則が作られ、何となく『自主規制』というか、企業がこの辺をしっかりと考えていこうという方向に話は進んでいました」(江間氏)
しかし、ここで欧州から「AI法で取り締まるべきだ」と横やりが入った。これにより「ハードローで法律を作り罰則規定を設けるべきだ」とする欧州と、「問題が起きてから対処しよう」という米国、「品質保証や標準化にも力を入れていこう」とする中国など、さまざまな意見が乱立する状況となった。さらに生成AIの登場により「ユーザー側も利用方法を考える」必要が生じ、「問題がごちゃごちゃになってしまった」のが2023年頃だという。
そうした中で現在につながる重要なキーワードが登場する。それが、2023年開催の「G7広島サミット」内で国際的なAIガバナンスのあり方として示された「インターオペラビリティ(相互運用性)」という考え方だ。
インターオペラビリティとは、異なる組織やシステムが連携して機能することを指す。広島サミットで示された方向性は「ハードローかソフトローか」といった違いはあれども、他の国や地域で出されているガイドラインの内容に、それぞれのやり方で対応していればそれでよしとするものだ。透明性の観点からも、各自の制度が「きちんと対応している」ことがわかるようレポートなどで公開されていれば、「国際的にも皆同じ一定の基準に達するのではないか」という議論になってきているという。
「今OECDが事務局となって、大規模言語モデルなどを開発している企業などに、ボランタリーに自分たちがどういう取り組みをしているのかを4月ぐらいまでにレポーティングしてもらうよう呼びかけています。それがうまく行けば、自主規制ベースで安全や公平性などに対応していることが確認できる枠組みができると考えられています。ただ、そこで出てくるものがボロボロだったり、全然レポートになっていなかったりすると、『本当にその枠組みでできるのか』『やはりハードローで罰金をつけないとダメなのではないか』といった議論になるので、そこがひとつ注目ポイントになるかと思います」(江間氏)
江間氏によると、この流れは日本においても同様だ。大枠としては(ハードローで規定するのではなく)相互運用するため、各組織内で2016年頃から議論されている要素(「プライバシーやセキュリティの問題」「AIのバイアスの問題」など)への対応を、皆がわかりやすいよう「その都度報告」することが求められるとのこと。
「そうした流れがあるので、2016年頃から議論されてきたポイントに対して、各組織の中で『どう対策していくのか』『誰が対応できるのか』『そういう人材を育てるべきなのか』といったことをしっかりと見ていくことが、これからのルールメイキングで大事になります」(江間氏)
さらに江間氏は、日本の企業に「伝えたいこと」として以下のことを言い添えた。
日本の企業や団体には、日本人的気質として「ルールは決めてくれたら、どんと受け止めて適応する」という「“強気な”受け身の姿勢」でいるところが多い。しかしAIのルールメイキングは「今動いている」状況にあるため、「ルールメイカー(ルールを作る)側に回れる」チャンスがいくらでも転がっているという。
「つまり『これは変えてほしい』『これは嫌だ』といった声を皆で出していくことで、どんどん(ルールを)変えていけるということが前提としてあるわけです。ですから受け身になるよりは、どんどん声を上げるためのチャネルを増やし、自社や自組織の中で人材を育てていってほしいと思います。そうするとルールメイカーになれます。それが今のAI(業界)の一番おもしろいところじゃないかと思います」(江間氏)
* * *
イベントの当日JDLAは、日本企業のAI活用を促進するために設立された「法と技術の検討委員会」(2024年11月〜)での議論の成果を公表したほか、企業向けの「相談窓口」の設置も発表した。
こうした取り組みを活用することも、江間氏の言う「声をあげる」ことにつながるだろう。これを機に多くの日本企業がルールメイカー側に周り、この先のAIビジネスを優位に進める契機をつかめればと願う。






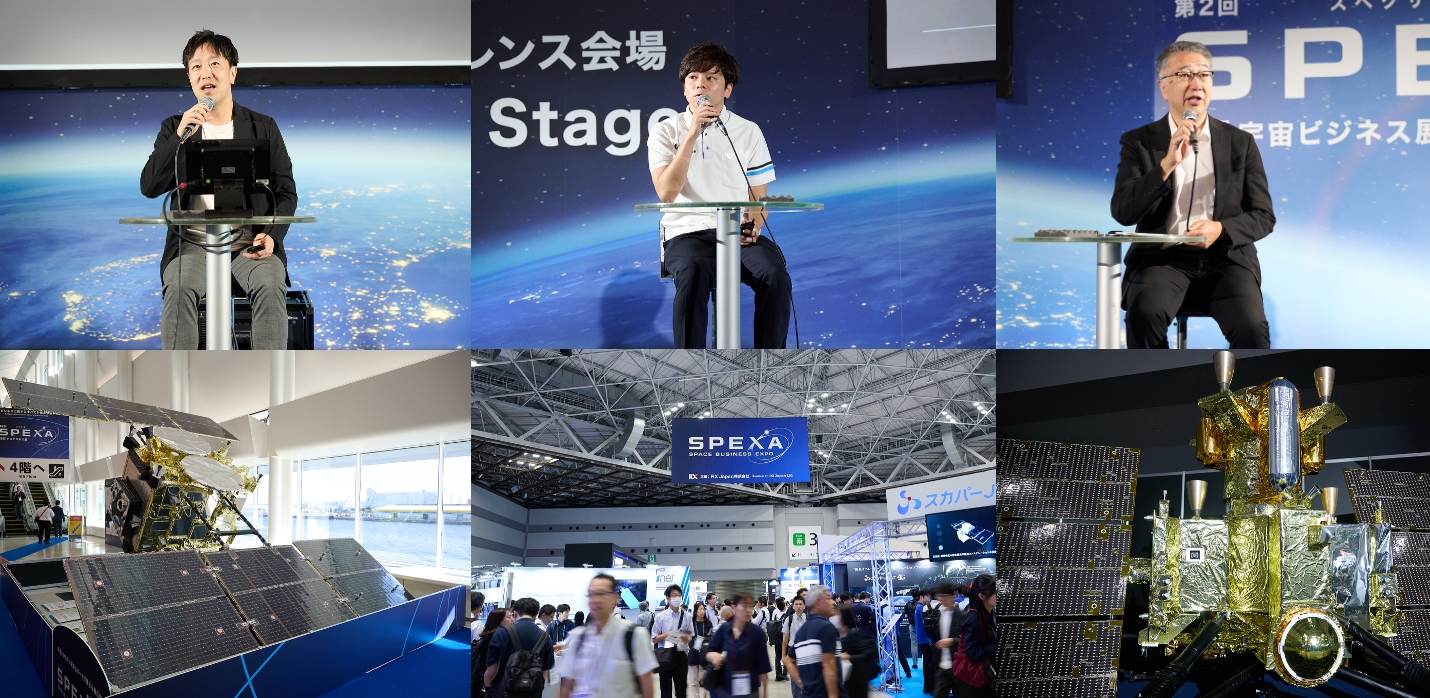






 ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり
ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり