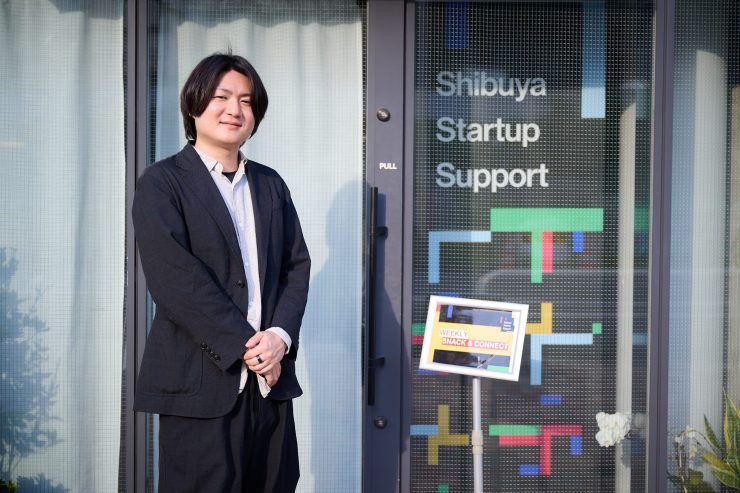近年、資源の循環を目指すサーキュラーエコノミー・スタートアップが多数誕生している。その中で「寝具」などのリサイクルを展開し「日本を廃棄大国から資源大国へ変える」をビジョンに掲げるのが、株式会社yuni(本社・東京都渋谷区、2019年設立)だ。
yuniは、寝具などに使われている綿、ポリエステル、羽毛、ウレタンなどを、自治体・企業・個人から引き取り、再生素材化する「susteb」を2021年から展開。和歌山県和歌山市、神奈川県横浜市、山梨県富士吉田市、宮城県栗原市、千葉県四街道市、埼玉県朝霞市で、寝具等の廃棄物を再生素材化する実証実験を重ねてきた。現在は、兵庫県、山梨県、大阪府に再生工場を構えるなど着実に事業実績を拡大している。
また、寝具再生だけに留まらず、地域で排出される資源性廃棄物(資源ゴミ)を同じ地域に再生材として供給する「ローカルな素材循環を実現するAI資源循環システム構築・実証事業(以下、「AI資源循環システム」)は、環境省の「令和6年度補正予算 地産地消型資源循環加速化事業(モデル事業)」として採択された。
こうした一連の取り組みや、起業に至る動機について、同社代表取締役CEOの内橋堅志氏に話を聞いた。
原点は実家の寝具メーカーでの“違和感”
yuniは、内橋氏が起業した2つ目の会社だ。もともとAIエンジニアをしていた内橋氏が最初に立ち上げたのは、ビットコイン関連の会社だった。事業は軌道に乗ったが「(暗号資産の相場上昇で)銀行口座の数字が増えるのを眺めているうちに、 “稼ぐ実感“が持てなくなった」という。
そんな折り、頭に浮かんだのが、高校生の頃に手伝っていた実家の寝具メーカーでの経験だ。内橋氏の実家では、綿やポリエステルなどの素材を購入し、寝具やクッションなどを製造していたが、その際に出る大量のゴミのあり方に違和感があったという。
「(顧客によっては)『床に落ちた素材は捨てる』というルールがあり、床に落ちた素材はゴミとなりました。たとえば『1kg300円』で購入した素材が、床に落ちた瞬間に、全く汚れていないのに『0円』になる。この“価値の下落”に大きな違和感があったのです。しかも、そのゴミの廃棄にはお金がかかるのです。当時の私には衝撃的でした」
この違和感を解消する事業であれば「(失っていた)仕事へのやりがいを見出せるのではないか」と考えた内橋氏は、実家の工場を利用してゴミの「再生素材化」を研究開発する会社を立ち上げる。これがyuniの始まりだ。
2度目の起業にあたり、強く意識したのが「アービトラージ(Arbitrage、裁定取引)」という考え方だという。アービトラージとは、同一(あるいは類似の)商品が、異なる市場で価格差が生じている際に、割安な方で購入し、割高な方で販売することで、利益を得る取引手法を指す。
「要は、異なる市場の価格差で儲けることを言います。私はこのアービトラージこそがビジネスの本質だと捉えていて、価値(価格)が変わる瞬間というのは、大きなビジネスチャンスだと思うのですね。(布団工場で違和感を持った)ゴミはまさにこれに当てはまります。こうしたところにチャンスを見出そうと立ち上げたのが、yuniです」
リユースではなく再生素材である理由
「susteb」とはどのようなサービスなのか。内橋氏によると、粗大ゴミで、一番点数が多いのが寝具だ。そしてその約98%が焼却処分されてきたという。こうした寝具などのゴミを自治体や企業、個人から回収し、綿やポリエステルなどの素材を「再生素材化」するのが「susteb」だ。
「susteb」運営にあたって、寝具の「リユース」ではなく、「素材を再生する」ことに強いこだわりを持っているという。
「なぜならリユースは既存産業を圧迫してしまうからです。たとえば、寝具メーカーが1万円の布団を作り販売しているところに、5千円のリユースの布団が出回ると、心が折れてしまいますよね。一方、再生素材の提供は寝具メーカーを助けることにつながります。再生素材は(国内で再生した時点で)“国産”です。国産素材を安定供給できれば、コストも下がり、国内メーカーの競争力は向上します。既存産業を助けるという意味で、再生素材はとても重要な役割を果たすのです」
加えて同社がこだわっているのが「独自のリサイクル手法とそれに必要な機器の開発」だ。
そのポイントとなるのが、一般的な製造プロセスを「逆回し」する発想だ。たとえば、綿布団。そのふんわりとした素材は、多年草のワタ(綿)の種子毛からとれる繊維(綿花)だ。これを集めて薄く長方形の形に整え、さらにそれを何枚も重ねることで厚みのある布団に仕立てている。
これを逆回しする際には、まず(使い古され“せんべい布団”のようになった)生地をバラバラに切る。切ったものを洗浄し、不純物を取り除いたら、これに風をあて、最初の綿花のようにふんわりと仕上げるという。
「綿以外のものも、こうした逆回しの発想によって最初の状態に近づけ、再生素材として提供しています。こうしたリサイクル手法を自社開発できる点も、我々の強みとなっています」
キャッシュポイントは2つ
もうひとつ、大きな強みとして「回収・再生プロセスの最初と最後の2回、収入が発生する 」ことがあげられるという。
一般的な製造業であれば、素材を仕入れ、製品を作り、それが売れた段階で収入が生じる。これに対して、同社のビジネスモデルでは、再生から素材・製品納品までを一括で契約し“有償”で受けるモデルがある。
「つまり、最初にキャッシュポイントが発生することがあるわけです。たとえば1枚500円で布団を回収し、リサイクルにかかるお金が300円だとすると、その時点で200円の利益が出る。つまり、素材がまだ売れていないのに、すでに利益が出ているわけです。後はこれを売りさえすれば、確実に儲かる状況になっています」
ただし再生素材のものづくりでは、回収したゴミは全て再生して売り切らなければならない。「100tのゴミが入ってきた時に、60t売れて、40t残ったというのでは契約違反でダメ。とにかく『流し続けること』が大事です」
そこで内橋氏らは、自動車の樹脂に混ぜる素材として購入してくれる会社など「低価格だけど、膨大な再生素材を購入してくれる相手」も確保したうえで、「利益率の高い販路」も開拓する戦略をとっている。
「こうすることでリスクを確実に回避しつつ、継続的に事業を拡大することに成功しています」
資源ゴミ流通の仕組みをAIでスマート化
冒頭でお伝えしたように、yuniは今年7月に、環境省のモデル事業に採択され、「AI資源循環システム」の開発を発表している。
これまで内橋氏らは、誰も手をつけていない「寝具のリサイクル」に可能性を見出し、事業を拡大してきた。こうした取り組みを進めるうちに、「プラスチックなど他の資源ゴミのリサイクルもできないか」と相談されることも増えてきたという。
「他の資源ゴミは、すでにリサイクルの事業者がいるので、基本的に我々は参入しません。ただ、参入はしないのですが、資源ゴミに関しても、既存の事業者と連携したうえで、たとえば我々が回収を一手に引き受け、他の事業者に回すなど、流通の仕組みをもっとスマートにできないかと考えました。これが『AI資源循環システム』開発の発端です」
内橋氏が構想する「AI資源循環システム」は、(将来的にyuniが回収を引き受けるであろう)地域のさまざまな資源ゴミの、効率的な識別・分類、最適な処理・再利用プロセスの選定にAIを活用する。
たとえば、ある企業が鞄を作るのに再生素材を使おうと考えた時に「必要な再生素材を提供してくれる業者は?」と質問するとAIが必要な情報を回答する。あるいは、その時々の各事業者のキャパシティに合わせて、資源ゴミの振り分けを自動で行う。また、再資源化できそうな廃棄物をかかえる個人や企業に、適切なパートナーとなる事業者の情報を提供する。
「このシステムが実用化されると、再生素材を使いたい企業、再生素材を作る事業者、資源ゴミを捨てる個人や企業の3者にメリットがもたらされます。さらに(システム全体を俯瞰している)当社ではニーズがあるのに再生素材化されていない資源ゴミが何であるのかが見えてくる。そうしたら、その資源ゴミを再生素材化する仕組みを作ることで、我々の収益も増えるのではないかと期待しています」
内橋氏によると、現在多くの自治体でゴミ処理にかかる費用が高騰している。一方で、ゴミの再生素材化の技術が向上しており、近い将来「ゴミを焼却処分するよりも、再生素材化する方が安くなる可能性が高い」という。
そうなると、yuniがビジョンに掲げる「日本を廃棄大国から資源大国へ変える」ことも夢ではなくなるだろう。内橋氏らの取り組みが、その大きな原動力となることを期待したい。