グーグルの挫折と新型コロナ対策から見えてきた「スマートシティ」へ続く道

ほぼ無人と化したニューヨークのタイムズスクエア。従来の構造の都市では、パンデミック化で都市活動を継続するのは至難だ。3月16日撮影(撮影・新垣謙太郎)
米グーグルの親会社アルファベット傘下のSidewalk Labsは、カナダ・トロントで進めていたスマートシティプロジェクトを中止することを5月7日に発表した。Sidewalk LabsのCEOダン・ドクトロフによると「(新型コロナウィルス等の影響によって)プロジェクトの収益性を確保することが非常に困難になった」ためだという。
トロント東部の臨海地区に広がる広大な敷地に、5000万ドル規模を投じる計画だった同プロジェクトは、世界各地で進められているスマートシティ開発のなかでも特に注目されていた。その計画の中止はスマートシティ開発の先行きに影を落とすことになりかねない。
こうした一方で、相反する潮流もある。世界が直面するパンデミックの対抗策としてスマートシティの有用性が再認識され始めているのだ。
通信分野に特化した米・調査機関ABIリサーチのCROスチュアート・カーローは、2020年3月に出したレポートで、「(新型コロナウィルスの影響によって)世界中のすべての都市が、都市の防災力(Urban Resilience)をめぐり、より責任ある取組体制を採用することになる」と述べ、スマートシティの原動力となるAI×データ産業への投資が大幅に促進される可能性を示唆した。Sidewalk Labsのダン・ドクトロフも、「プロジェクトの継続は止めたが、現在の衛生的な危機で、将来のために都市を再設計することの重要性を認識した」と従来型と都市の“スマートシティ”への変革は必要であるとの認識を示した。
必要なのは生活圏全域に配置されたセンサー群
そもそもスマートシティの定義とは何か。自動走行やキャッシュレス、ドローンによる物流などの住民サービスがその特徴として語られるが、統一された定義は存在しない。
ニューヨーク市立大学工科校でデータドリブン・サステナビリティの研究を行う中村正人准教授は、スマートシティの最もシンプルな要綱として「『大量のセンサー群でビッグデータを取得』し、『AIのアルゴリズムで処理』を行い、『IoTを通じて実生活にフィードバック』する機能を有した都市」を挙げる。
「特に重要になるのがデータの取得です。データがなければAIのアルゴリズムは育たない。そしてデータを取得するためには大量のセンサーが必要になる。つまり、スマートシティが実現された社会とは、身の回りのすべてのモノがセンサーを有し、都市におけるあらゆる事象がデータ化される社会と定義できます」
そして、このデータ化こそが「パンデミックに対する強力な武器となる」と中村准教授は語る。人々が街なかをどのようなルートで移動したか、接触の履歴、メールやSNSで書かれた感染の報告……こうしたビッグデータを収集・分析することで、感染ルートや感染クラスタの特定、隔離を迅速に行い、感染拡大を封じ込めに役立つからだ。
スマートシティの入口は身近に
こうした取組はすでに始まっている。確かにスマートシティの完成像として語られる「あらゆる場所にセンサーが設置された都市」の実現はまだ先だが、実はすでに私たちの身近な場所にセンサーと、そこから得たデータを利用できる環境がある。スマートフォンを活用するのだ。
スマートフォンはコロナ対策でも活用されている。その一例は、濃厚接触を追跡するアプリだ。グーグルとアップルが共同で、追跡アプリのためのAPIを開発したこともあり、この試みは大きな注目を集めている。この「濃厚接触追跡アプリ」では、Bluetoothの無線信号により一定の範囲内に同アプリの利用者がいることを認識できる。利用者同士が近接して数分以上留まれば、両者のスマートフォンに固有の識別コードが生成される。つまり、両者が「接触」したという記録が残るのだ。そして新型コロナウィルスに感染していると診断された場合は、アプリを通じて報告すると、直近2週間に接触した他のユーザーに、感染拡大を防ぐためのアドバイスが通達される。
類似の追跡アプリの先行事例として有名なのはシンガポール政府が国民に提供している「Trace Together」だ。4月中旬までに100万人以上がユーザー登録した。ユーザーの感染が発覚すると保健省によるヒアリングが行われるが、過去の接触者をBluetoothの信号で記録する点は同じだ。シンガポールが初期の感染者数を低く抑えられた背景にこうした追跡アプリの貢献もあったといわれている(ただし、同国は4月後半に入って感染が拡大してしまった。その理由については後述する)。
中村准教授は、「このシンガポールの事例は、スマートシティの機能が現実に成果をあげたわかりやすい例」と指摘する。
「『スマートシティを実現する』といって官僚などが音頭をとっていますが、それが具体的にどういうものなのか、多くの人にとってイメージしづらいものだと思います。その本質はデータを処理することで都市の問題を解決すること。その点で、シンガポールの施策はまさにスマートシティに期待される機能です。すなわち、スマートシティとは突然現れるものではなく、機能の追加と拡充を繰り返し、いつのまにか実現されているものと考えられます」
今回のコロナ禍で、従来の都市からスマートシティへと移行が加速するのは想像に難くない。スマートシティで実現される自動化・リモート化は人の接触を減らすという点で感染防止に効果がある。その手始めがこの追跡アプリだ。
課題はやはりプライバシーの問題
しかし、スマートシティの実現には課題も多い。最大の懸念は接触履歴などのプライバシーと密接に関連したデータを、個人の権利を侵害することなく管理する枠組みをどのように構築するかだ。「Trace Together」やグーグルとアップルの共同プロジェクトでは、個人の特定に結びつくデータはサーバーに残らないと強調されている。しかし、緊急事態という大義名分のもと、こうした前提がなし崩しになる可能性もあり、パンデミックとはまた別種のリスク要因になり得る。
実のところ、Sidewalk Labsのトロントでの挫折も、このプライバシーの問題があると多くのテック系メディアが推測している。プロジェクト開始当時から、データの管理・取り扱いについて住民から根強い批判があったのだ。スマートシティの開発とプライバシーの保護を両立するために、今後どういったアプローチが必要となるのか。先出の中村准教授は語る。
「プライバシーに関わる問題を扱う時に考えるヒントになるものがふたつあります。ひとつは、情報の非対称性からくるギャップを認識すること、もうひとつは一般住民の認知・受け入れ・普及の時間差についてです」
情報の非対称性からくるギャップとは、すなわち開発者と住民の情報に対する意識の差だ。社会が「管理される側」と「管理する側」に分かれるのではとの危惧を住民が抱くことになる。
「経済学や契約理論でインフォメーション・アシンメトリー(Information Asymmetry)と呼ばれますが、人は他人の情報を持ちたい(例:「レストランがどれだけ混んでいるか」等)一方で、自分の情報を開示するのをためらう(例:「どのレストランに今自分がいるのか」)傾向がある。スマートシティの利便性がそれによって起こりえるプライバシーの不安を大きく上回るものでなければ、住民に理解は得られません。つまり利便性をうまくアピールし、プライベートな情報を少しずつ共有してもらうことがスマートシティの成功のカギであり、課題なのです」
もうひとつの「一般住民の認知・受け入れ・普及の時間差」は、テクノロジーが万人に受け入れられるまでには、一定の時間が必要になることだ。この事実を念頭にスキームを組まなければ、プロジェクトが失敗する可能性が高い。
「イノベーションや新しいプロダクト・システムはテクノロジー・アダプション・ライフサイクル(Technology adoption life cycle)に沿って徐々に世の中に浸透していきます。現金からクレジットカード、暗号通貨へと至る流れを思い浮かべてみてください。クレジットカードの誕生は諸説ありますが1950年。現在ではなくてはならないものですが、履歴が残らないことやセキュリティの観点から現金が好まれるケースはまだまだある。通貨の最も新しい形である暗号通貨では、そうした不安はさらに大きい。これは既存の都市からスマートシティへの移行においても同じことがいえます」
感染者増加で判明したさらなる課題
パンデミック対策としてスマートシティを考えた際、今回のコロナ禍はプライバシーとは別の課題も浮き彫りにした。いかにデータを収集・分析し、問題解決のための方法が提示されても、各人がそれを実行できなければ意味がない。ここでもシンガポールが例になる。
3月23日に510人未満だった同国の感染者は、5月20日現在で約2万9000人。その多くはシンガポールに100万人以上いる外国人出稼ぎ労働者だ。彼らの生活環境は、感染から身を守れる状態ではない。英ガーディアン紙によると、多くの外国人労働者は1部屋につき12~20人が2段ベッドで眠り、毎日トラックの荷台に詰め込まれて仕事場へ向かう。仮に彼らがアプリによって感染リスクを承知していても、自衛のための行動をとる余地がないのだ。
スマートシティの恩恵を得るにはすべての都市生活者が、データ分析の結果最適とされた生活様式が実現できる必要がある。それには社会・産業構造にまで踏み込んだ都市の在り方と暮らし方の根本的な改変が必要になる。
パンデミックが現実となった世界において、スマートシティの有用性は明らかだ。だからこそ、私たちの一人ひとりがその実像を理解し、プライバシーについて、さらには自分が暮らす社会の仕組みや在り方について再考するべき時期が来ている。



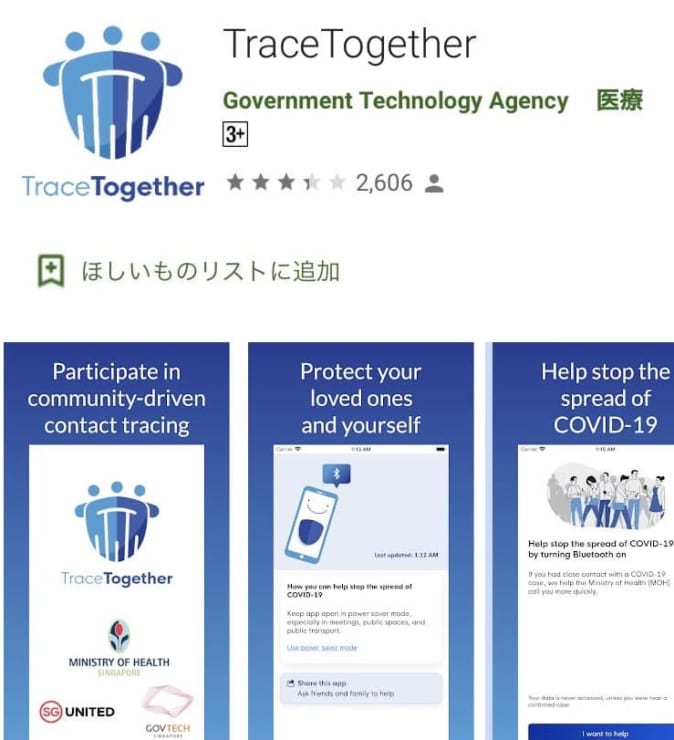

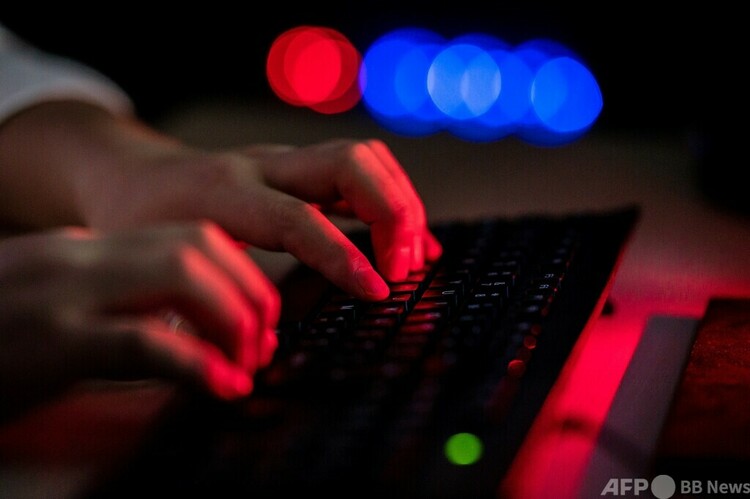







 ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり
ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり