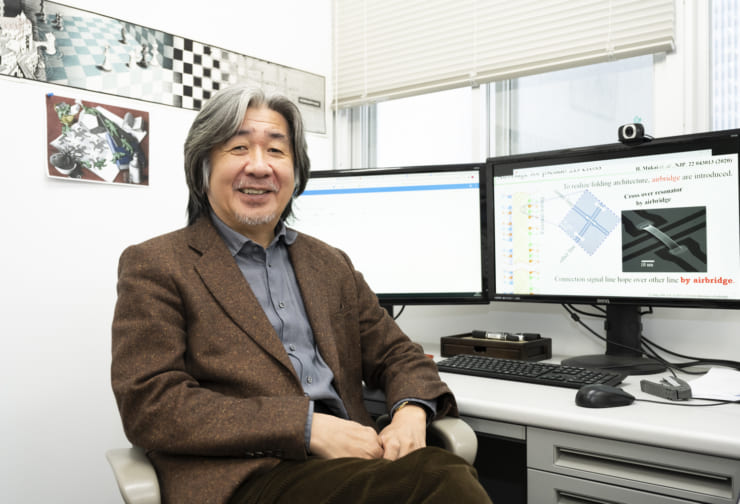「コロンブスの卵」とは「だれでもできそうなことでも、最初に行うことはむずかしいということ(コトバンク『大辞泉』より)」。実用化にはまだ課題がある量子コンピューターの分野において、この「コロンブスの卵」的な発想が登場した。これにより量子コンピューターの開発が加速されるかもしれない。それは、東京理科大学理学部第一部物理学科の蔡 兆申(ツァイ ヅァオシェン)教授らによって提示された「超伝導量子コンピューターの新規回路方式」だ。
大規模な情報を扱うことができる量子コンピューターを作るには、量子ビットと呼ばれる素子を数多く組み合わせて、集積回路(「論理量子ビット」)を構築する必要がある。これは、古典コンピューター(従来型のコンピューターを量子コンピューターと対比してこう呼ぶ)における演算装置にあたるものだ。
この集積回路では、まず隣り合う量子ビット同士を格子状に配線でつなぎ、さらに一つひとつの量子ビットを、その振る舞いを制御する装置とつなぐ必要がある。
ただし量子ビットは磁気や熱など周囲の影響(ノイズ)を受けやすいため、半導体チップ製造などに用いられる積層型の配線技術は使えない。
このため従来の回路方式では、まず量子ビットを平面に格子状に並べてつないだ後、量子ビットを制御するための配線は上から垂らしてつなげる必要がある。こうして立体的な構造(3次元配線)になると、回路の中央部にある量子ビットへの配線などが難しくなり、これが量子コンピューターを構築する際の壁のひとつとなっている。
蔡教授らが提示した「超伝導量子コンピューターの新規回路方式」では、こうした複雑な構造が不要になり、量子コンピューターの集積回路を簡単に作れるようになる可能性が高いという。
では新規回路は具体的にどういったものなのか。また今後の量子コンピューター開発にどのような影響があるのか。蔡教授に伺った。
「伸ばして、折り畳む」新発想
量子コンピューターは、量子状態となった量子ビットの特性(重ね合わせや干渉)を使って計算するものだが、量子ビットを制御する方法には、いくつかの方式がある。このうち、グーグルなど量子コンピューター開発に取り組む企業の多くが採用しているのが、超伝導型だ。
蔡教授らが提示した新規回路方式は、この超伝導型の量子コンピューターを構築するためのものとなる。
では新回路方式とは具体的にどのようなものか。蔡教授によると、その作り方は以下の図のようになっている。
まず平面上に並べた量子ビット(図a)の配線を、「図b」のように長く伸ばす。
次に量子ビットの各列で、折り紙のように順々に折り返していく。すると、「図c」のように、量子ビットの列が回路の外側に並ぶ配置になる。これが、蔡教授らが提示した新回路方式だ。
「この新規回路方式を用いることで、内側にあった量子ビットを引っ張り出し、外側に並べられるようになります。外側に並べることにより、立体構造が不要となり、半導体メーカーなどが持つ既存の配線技術を使って、簡単にアクセス(配線)できるようになるのです」(蔡教授)
ちなみにこの方式では、量子ビットをつなぐ配線の一部が交差するが、配線を浮かせる既存の技術(「エアブリッジ」)を用いることで、混線を避けられるという。
従来方式の“配線問題”を解消できる新規回路方式だが、その作り方自体は至ってシンプルなものに見える。そう伝えると、蔡教授は「コロンブスの卵的な発想です」と笑いながら答えた。「簡単な話ではあるのですが、今まで誰も思い付かなかったのです」(蔡教授)
真に実用的な量子コンピューターを作るために
蔡教授らの研究グループは、新規回路方式を採用する影響についてさまざまな角度から検証を重ね、約(30×30=)900から(40×40=)1600の量子ビットの集積規模であれば「特に問題がない」という結論に達している。
実はこの「約900以上」の量子ビットに新規回路方式が対応できるという点が重要となる。
一般的に、演算精度が高い、実用的な量子コンピューターを作るには、計算エラー(誤り)を訂正する仕組みが欠かせないと言われている。
古典コンピューターにおいても計算エラーは頻繁に起こっているが、計算の答えを複数のビット(素子)で算出し、多数決で決める仕組みを備えているため、最終的に出てくる答えはほぼ100%正しくなる。
量子コンピューターにおいても、こうした「エラー訂正」の仕組みを構築しようとしている。ただ量子ビットは一度観測してしまうと量子状態が壊れてしまうため、計算途中で誤りをチェックすることが難しく、複雑な仕組みが必要となる。現時点では「表面符号エラー訂正」という方式が有力視されているが、これを実現するには、ひとつの集積回路に「少なくとも約900量子ビットが必要」(蔡教授)だという。
ここで新規回路方式が「約900以上」の量子ビットの集積化に対応していることが効いてくる。つまり新規回路方式は、エラー訂正に対応した、実用的な量子コンピューターの開発につながる方式だというわけだ。
「しかもこれはスケールアップが可能です。これくらい(900量子ビットほど)の規模で作れば、それをひとつのユニット(チップ)としてたくさん並べ、さらに大規模な情報を扱えることもわかっています。世界中の研究者がこれを目指して尽力しているのではないでしょうか」(蔡教授)
ただし、大規模な回路を作ることができたとしても、「量子ビットを制御する課題」が残ると蔡教授は指摘する。
古典コンピューターでは、電気回路に信号を入力すれば、あとは自動で計算してくれる仕組みになっている。しかし量子コンピューターでは、一つひとつの量子ビットを、時間軸に沿って正確に「制御」しなければならない。
「その操作は、音楽を演奏するようなもの。量子ビットは言わばピアノの鍵盤です。その鍵盤を、ものすごいスピードで、(正解率)99%以上という高精度で叩かなければいけません。しかも900の量子ビットを扱うには、900もの制御装置が必要ですから、それも大変な作業です」(蔡教授)
“夢のコンピューター”と言われる量子コンピューターの実用化には、越えなければならない山がまだたくさん存在する。しかし蔡教授らの新規回路方式が提示されたことで、その山のひとつを越える可能性が高まったことは間違いない。実用化の歩みがさらに加速することを期待する。