札幌のweb3スタートアップが仕掛けた「ふるさと納税返礼品にNFTアート」の可能性

2月に札幌で開催されたweb3トークイベントにて。中央が畠中氏(写真提供:あるやうむ)
ふるさと納税の返礼品として、NFTアートを採用する自治体が現れている。今年の5月には、北海道余市町が、人物像と町の特産物のワインなどの絵を組み合わせたNFTアートを返礼品として提供したことは、当媒体の記事でも紹介した。同町では、その後もブロックチェーンゲーム「My Crypto Heroes」のNFTアイティムを返礼品として採用している。また、兵庫県加西市も、ブロックチェーンゲーム「クリプトスペルズ」上で使えるNFTのカードを、ふるさと納税の返礼品として採用することを公表している。
地方自治体のデジタル化は、日本の重要課題であり、岸田内閣はNFTなど、web3にも積極的に取り組む方針を掲げている。こうした環境下で、なにかしら“デジタル”それも”web3”的な取り組みを新たに始めたいと考えている市町村も多いことだろう。
ふるさと納税とNFTアートの組み合わせは、自治体の取り組みをPRするには絶好の取り合わせではあるが、地元企業の商品や海・農産品とは異なり、NFTアートを返礼品として提供するにはそれなりの知識や準備が必要となる。そうした点で自治体のバックアップをしているのが、株式会社あるやうむ(本社・北海道札幌市)だ。
NFTアート提案の過程で触れた自治体職員の熱意
あるやうむは、代表取締役の畠中博晶氏が2020年11月に創業したスタートアップ。畠中氏は、早い時期から札幌市で起業することを構想していた。大学在学中から仮想通貨のトレーダーとして創業資金の準備を始め、卒業後、株式会社JPYCでの勤務を経て、かねてからの構想通り札幌の地にあるやうむを創業した。
創業当初のビジネスとしては、キャラクターグッズの販売などを手掛けていた。その後、とあるきっかけから、NFTと地方創生の掛け合わせには可能性があることに気付き、ビジネス上のアドバイザーからの助言で、ふるさと納税の返礼品としてNFTアートを提案することを始めた。
畠中氏は仮想通貨トレーダーとしての実績はあるものの、自治体ビジネスへの参入はこれがはじめて。自治体への営業は、他のSaaS企業で公共セクタへのサービス導入で実績を積んできた営業責任者・渉外担当の稲荷田和也氏が参加することで前進する。全国の自治体向けの媒体に折込チラシを入れて告知したところ、約10程度の自治体から問い合わせがあったという。しかし、問い合わせがあった市町村から最初の採用例が出たのかというと、そうではない。
ある自治体では、返礼品となるNFTアートの発注にまで話が進み、順調に進むかに見えた。しかし、前例のない取り組みに職員が萎縮したためか、先方から急遽中止の連絡が入り、話はそのままお蔵入りになってしまった。
こうした苦い経験もあるが、概ね問い合わせをしてきた自治体の担当者は「情報感度が高くて、やる気もある方々が多く、お話していてこちらが刺激を受けることもありました」(畠中氏)とのこと。実際、新たにNFTアートを返礼品に加える予定の兵庫県加西市などは、NFTアートの返礼品ありきで話が進んだわけではない。「シティープロモーションや移住、ふるさと納税などを担当されている方が、『スタートアップを地方に根付かせる』という当社の理念のひとつに興味を持ってアプローチしてこられたのです。何回か意見交換させていただいて(NFTアート)の提案になりました」(稲荷田氏)。
デジタル化の取り組みについては、なにかと批判にさらされることの多い日本の市町村だが、畠中氏は「(こうしたやり取りを通して)全国の自治体の中にはすごく頑張っている職員のみなさんがおられるというのを感じました」と、地方のポテンシャルをあらためて実感したと話してくれた。
返礼品としてのNFTアートの課題と展望
先行して、NFTアートを返礼品に採用した余市町の場合は、町長が新規の取り組みに熱心で、前例がないことはあまり問題にならなかった。しかし、一般的に役所は新規案件には慎重だ。もちろん、あるやうむでは、事業開始に当たって、イラストのデータをNFT化してふるさと納税の返礼品として採用することについての可否を総務省に確認している。総務省からは「総務省告示百七十九号第五条五(編注※地域の広報目的で作られたキャラクターなどの扱い)に適合している場合は可能である」との回答も得ているので、実施は問題がない。
ただ、畠中氏によると総務省には「ふるさと納税の返礼品には、換金性や投機性のあるものは望ましくない」という見解があるという。この見解の対象となるのは、特にNFTアートに限ったことではないが、こうした懸念があることが障壁になることもある。「『できるけれども、望ましくはない』と国が言うと、国から都道府県、基礎自治体(市区町村)へ話が落ちていく中で、『望ましくはない』 という言葉が『してはいけない』 って(意識の中で)書き換わってしまって、1%でもそういう可能性があってはダメだ。みたいな解釈をしている方もいらっしゃるので、そういうところは大変です」(畠中氏)。とはいうものの、「投機性への懸念」があるのは理解できるので、この見解をNFTアートのために見直して欲しいということではない。
NFTアートは、実際には投機的な側面もあるので、返礼品として提供するに当たってはその投機性が表に出にくいような工夫をしているという。例えば、寄付の価格設定もあまりにも安く設定すると、転売で利益が得やすくなってしまう。ただ、商品の魅力を減じるような価格や機能設定にすると、返礼品としての魅力がなくなってしまう。そのあたりの制度・商品設計が難しいということを畠中氏は教えてくれた。
NFTアートの返礼品としての評判については、まだ実施例が少ないので、はっきりした傾向は見えない。余市町の場合だと申込者の内訳は、余市町のNFTアートを作ったイラスト作家(NFTクリエイターのPoki氏)のファンが3割ほど。NFTアートを所有してみたいけど、これまでどうすれば入手できるかわからなかったという人も全体の半分程度いたという。
NFTアートを返礼品としての採用することは、今後広がるのだろうか。あるやうむの他にも、大阪府泉佐野市と一緒になってNFTアートの返礼品を提供しはじめた企業がある。しかし、全国展開ということではあるやうむが、今のところは唯一であるらしい。畠中氏によると、余市町のように元々いろんな年齢、嗜好の人に向けて、さまざまな返礼品を持っている自治体ならNFTアートのような対象者が限られる返礼品であっても問題はないとのこと。
しかし、一般的にはふるさと納税の返礼品に新たに追加される商品は、多くの人にとって魅力的なもので、それによって「どれほど寄附金額をのばせるか」というところが評価ポイントになる。そういった事情をふまえると、NFTアートを返礼品として採用する優先度は高くないのかもしれない。
さらに、NFTアートを返礼品にするためには、NFTアートのシステムを提供できると同時に、ふるさと納税の特性やルールも熟知している必要があり、どんな企業にでも簡単に参入できるわけではない。
とはいうものの、いまのところ注目度は高くPR効果はある。今後、NFTアートに対する世間の理解がさらに深まり、アートとしての価値以外の機能、例えば新潟県の旧山古志村地区で試されているような、NFT所有者を関係人口として、地方創生になんらかの恩恵をもたらすエコシステムが出来上がれば、返礼品としての採用は急激に進むかもしれない。
あるやうむ関連リンク(プレスリリース)
「NFTによる地方創生」を推進する株式会社あるやうむが、ふるさと納税の返礼品としてNFTを採用する自治体を紹介する『ふるさと納税NFTマップ』を公開します。(2023年4月4日 リリース)



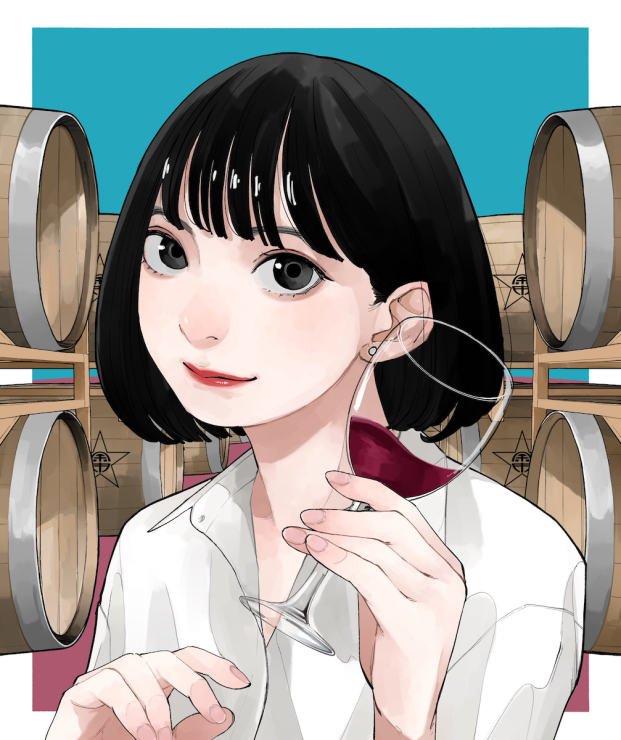

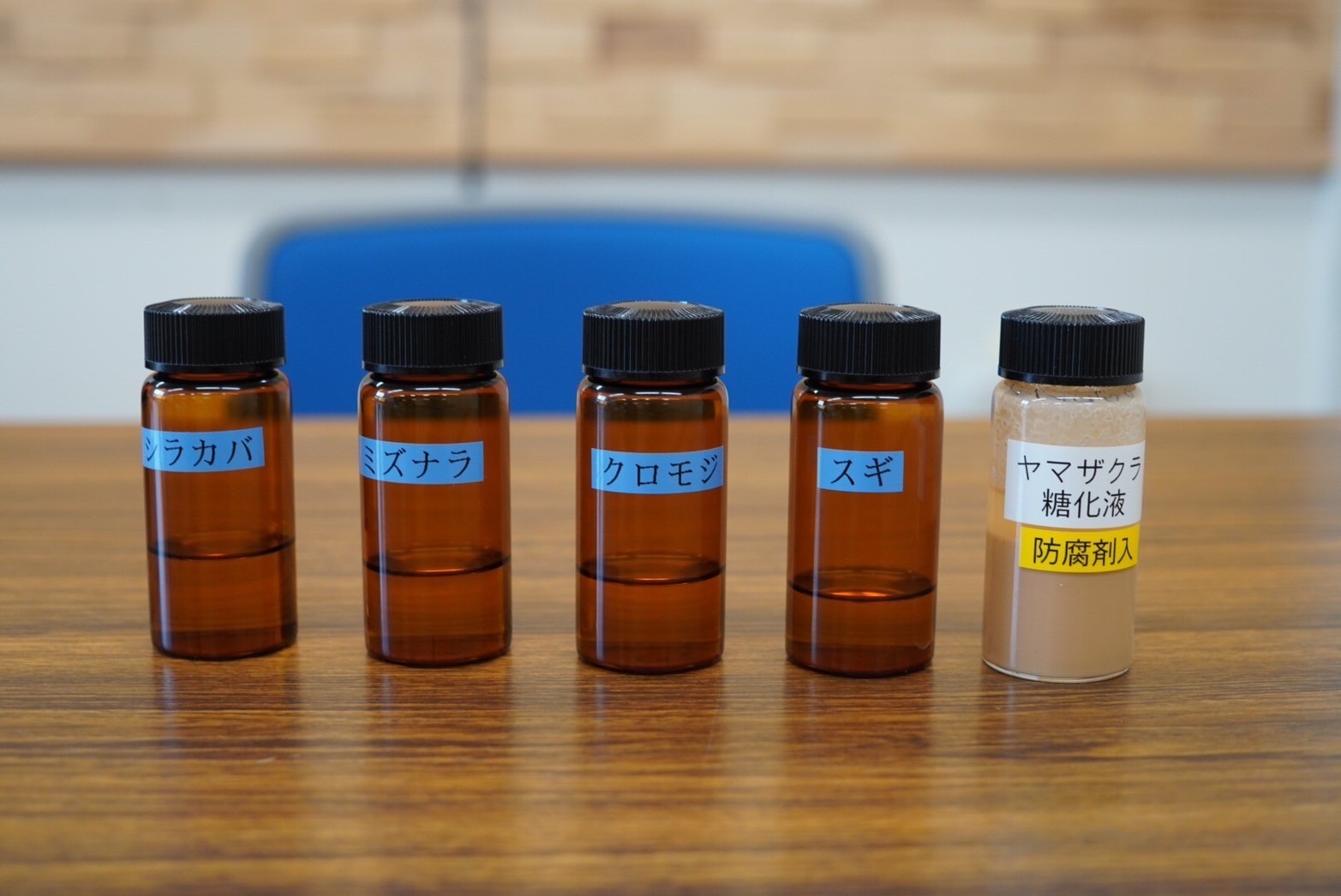








 ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり
ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり