商談を人工知能(AI)でアルゴリズム化 AIが自らを売り込む未来~松尾研究室発AIスタートアップ

株式会社ACESのメンバー(ACES提供)
東京大学松尾研究室発のAIスタートアップとして2017年創業した株式会社ACES(本社・東京都文京区)は、2022年3月に営業支援AIツール『ACES Meet』の正式リリースを発表した。
現在、ビジネスのさまざまなプロセスがDXされている。営業活動においてもマーケティングオートメーションにより、見込客を見つけてアプローチするまでのプロセスは効率化された。また、新型コロナの影響下でのオンライン商談も急速に普及した。このようにデジタル化が進む一方、商談中のどのポイントで失注したのか、どの言葉が受注に結びついたのかなど、優れた営業担当者のスキルやナレッジを共有することは難しく、属人的になりがちだ。
ACES Meetはこうした状況を打開するための、“売れる営業”と“普通の営業”の「差分」をAIで定量化するソフトウェアだ。
具体的には商談の動画から議事録を自動で書き起こし、それを話者ごとに切り分ける。それをもとに参加者が商談中どのタイミングで話したのかと、話をした時間の割合を表示する。さらに参加者の表情や動きなどを解析して、リアクションや感情の変化が大きかった瞬間を特定することで商談の重要シーンを共有しやすくする。さらに、広く普及している営業支援ツール『Salesforce』の商談管理機能との連携もワンクリックで行えるという。開発・提供元であるACESの代表取締役 田村浩一郎氏に話を聞いた。
属人化したものをアルゴリズム化
一見したところ、最近増えてきた議事録の自動作成のソフトウェアにも見える。しかし田村氏は、それらとは開発思想が異なると話した。
「『AならばBと指示に対する処理がルールベースに与えられたソフトウェア』と、我々が開発した『プロフェッショナルのインテリジェンスが組み込まれたAIのソフトウェア』はぜんぜん付加価値が違います」(田村氏)
ACES Meetによって書き起こしなどの作業から解放されるだけでなく、商談中の表情や発言などの解析から、今まで属人的だった「営業の秘伝のタレ」を社内で共有できれば成約率も高まるはず。そして、属人的な働き方をアルゴリズムに置き換えていくことは、社会的に大きな事業価値があり、その結果働き方に余白が作れると田村氏は説明した。
ACESは「アルゴリズムで人の働き方に余白を作る」というミッションと「アルゴリズムで社会はもっとシンプル」にというビジョンを掲げている。

ACESの創業は2017年11月。きっかけは、2017年の夏、学会のため泊まったホテルの風呂で、現在の創業メンバーと漫画翻訳を自動化するアイデアで盛り上がったことだった。さっそく出版社に漫画翻訳アプリの話を持ちかけたが「面白いが君たちって誰?」といぶかしがられた。
そこで、ACESの前身となる会社を登記し、6人のメンバーでマンションに事務所をかまえたが、漫画翻訳のプロジェクトは頓挫。半年間売り上げがなく「みんなでパスタばっかり食べて過ごした」と当時を振り返る。それでも、「ディープラーニングを社会実装できる人は少ない。こんなメンバーが集まっているのってもう2度とないチャンスだから、このメンバーでディープラーニングのポテンシャルに賭けて起業するのが一番いい」との思いから、DX事業に舵をきり、現在の事業の骨格が固まったという。
当時は修士の学生だった田村氏だが、会社を経営しながら松尾研究室で研究を続け、先月博士号を取得。「アカデミアとビジネスをつなげて、最先端の技術を社会実装することで付加価値を生み、その付加価値をアカデミアへ返していく社会的な循環を作りたい」と語った。
PoCで終わらない強み
ところで、ACESの事業はどのようなものなのだろうか?
「弊社の事業はAIトランスフォーメーションです。特に属人的な、ビジネスの中でも熟練の方の知見をAIアルゴリズムにトランスフォームして、デジタル上で事業を再現する実行しようというのが我々のやっている大きな事業のコンセプトということになっています」
こうしたコンセプトのもと、ACES にはビジネスモデルとして大きく2種類の事業形態がある。ひとつはDXパートナー事業で、もうひとつはAIソフトウェア事業だ。
「あくまでAIトランスフォーメーションするという事業の中で、提供の仕方、ビジネスモデルが違うというだけの話であって、本質的にやることは変わりません」
DXパートナー事業は、顧客の事業と並走し二人三脚で、その事業をAIトランスフォーメーションしていく。プロジェクトに参加し、課題を特定してAIアルゴリズムに落とし込み、事業をデジタル化していく。収益モデルとしては、プロジェクトフィーとそのAIのライセンスフィーの組み合わせになる。
ACESの強みについては、「ACESが参加して、PoC(概念実証)で終わったプロジェクトは一件もありません」と田村氏は胸を張る。
「『AIで何かできます』ではなく『ビジネス上何をすべきか』という事業の意思を必ず特定するところから始め、目標が定まったあと、AIアルゴリズムでどうするのかをデザインします。“AIバリューデザイン”と呼んでいますが、ここが我々のコアコンピタンスです」
できるだけ使われない方がいい?
AIソフトウェア事業は、ACESがパートナー事業の経験や研究成果から生み出されたものだ。今回の『ACES Meet』もそうして生まれた成果がソフトウェア商品になったもので、SaaSとして展開する。田村氏はソフトウェアの使い勝手については、ちょっと変わった観点を持つ。
「ソフトウェアとしての使いやすさとか、体験っていうのはすごく大事にしつつも、『AIのSaaSはどれだけ人に使われなくて済むか』というのが大事な考え方だと思うのです。『本当はもう全部やってくれればいいじゃん』っていうのがAIトランスフォーメーションなので、もちろん、すごく使いやすくユーザーの課題を解決するプロダクトを目指しているんですけど、ユーザーがAIを使っていることを意識しないぐらいがいい。理想をいえばミーティングが終わったら、『終わりました、まとめておきました、Salesforceにも入れておきましたよ』と言ってくれるAIプロダクトがいいじゃないですか」
ソフトウェアとしてACES Meetは進化中で6月には「要約機能」も付加されるとのことだ。
開発、事業進捗ともに順調であり、資金調達についても、創業以来、自己資金キャッシュフローでやっており黒字が続いているということだ。資金調達については急ぐことはないが、事業計画の中は織り込んでいるとのこと。
「創業から4年半ですが、“リアルの産業のAI活用、AIを活用したデジタルトランスフォーメーションにおいて日本をリードできる存在になれてきたかなと自負します」
この先の事業として田村氏は「ACES Meetを使えば、誰でもACES Meetを売れるようになる」ビジョンを持っている。つまり、人の営業スキルを学んだAIが、顧客開拓から、商談、成約まで営業の大半を自律的に行ってくれるという、あたかもシンギュラリティの世界のようだ。人間の営業担当は、ACES Meetの受注連絡を受けて契約書を作るだけでよくなるのかもしれない。いや契約書すら“作っておきました”とAIが言ってくれるようになる時代がそこまで来ているのかもしれない。










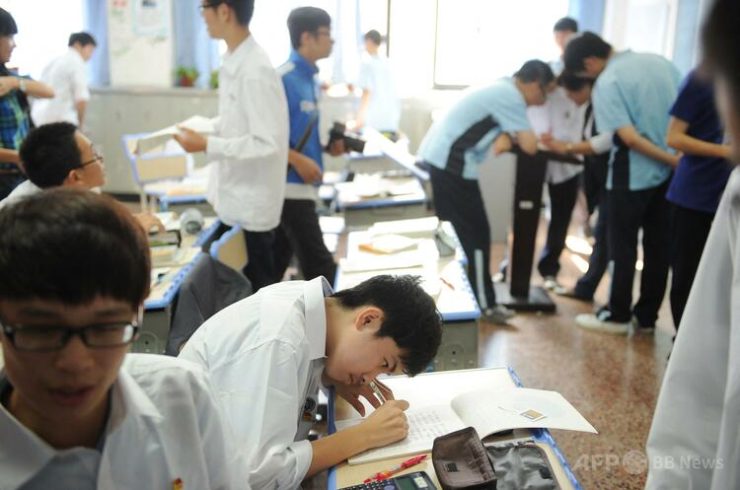

 スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs
スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs