「環境を守ったら儲かる」社会をめざして 生物多様性スタートアップのバイオームの取組み

株式会社バイオーム 代表取締役 藤木庄五郎氏
気候変動・地球温暖化のリスクについては広く知られ、ビジネスの世界でも企業の対策や情報開示が進んでいる。それに伴い脱炭素をサポートするスタートアップも多く誕生した。
環境に関する取り組みとして「気候変動」に続いて「生物多様性」の保全・回復の取り組みが今後求められるようになるが、この分野での起業はまだ多くはない。
研究ではなく起業を選んだ理由
株式会社バイオームは、2017年5月に代表取締役の藤木庄五郎さんが起業した。生物多様性を保全する取り組みを事業とするスタートアップとしては、草分け的存在だ。バイオームは、身の回りの動植物を撮影、記録して楽しめる「いきものコレクションアプリBiome」を提供している。京都大学農学部で森林生態学を本格的に学び、農学博士でもある藤木さんが、卒業後すぐにスマートフォンアプリのスタートアップを起業したのはなぜだろう。
「興味があったのは、環境保全。特に生態系を守ることですけど、調査の現場(ボルネオ島)で見たのは木を切って『環境を壊したら儲かる』といった現実でした。それで、研究するだけでは環境保全は上手くいかないなあと。『環境を守った方が儲かる』といったような、社会の仕組みの変革が起こらないとこの領域は解決には向かわないと思うようになり、それなら研究者ではなく、会社を作って環境保全で利益を出すということにチャレンジしたいなと」
「環境保全で利益を出す」。掲げた目標に対する社会の評価は、当時は相当に厳しいものだった。資金調達のために投資家との面談を重ねたが「『ボランティアでやりなさい』となんべんも言われました」と藤木さんは当時を思い出して苦笑する。
生物多様性の保全とビジネスがどう結びつくのか、確かにそれを想起するのは難しい。「『ポケモンGO』のリアル版みたいなもんです」というバイオームのアプリがどんなビジネスにつながるのか。なぜスマホアプリ開発を始めたのか。それを理解するには、藤木さんの学生時代の調査研究のエピソードに遡る必要がある。
スマホは最適なツール
生物多様性や生態系の実態把握が難しいのは、実際その場所に何があり、どうなっているのかは現地に行って見てみないとわからないことだ。生物多様性の指数の定量化をめざして研究を進めていた藤木さんも、研究者としてボルネオ島の熱帯林に長期にわたって滞在した。
「そこにどんな生物がいるのかという地上のデータを把握してないと、衛星を使ったリモートセンシングだけではその場所の生態系が解釈できないので、結局現地で生物の調査が必要になってしまうんです。つまり、(研究を進めてきた手法を)実用化しようにも(全部自分たちで現地調査するのは)大変すぎてできるわけがない。で、現地のデータを効率よく集める方法が必要だなって」
そこで、思いついたのがスマートフォンを使って、現地のデータを集めること。無線なのでボルネオでも通信が可能。生物同定に欠かせない画像情報はカメラで、位置情報はGPS取得できる。生物のデータ収集にはもってこいのツールだ。
藤木さんはバイオーム社のビジネスを説明する際「生物をデジタル化するんです」というフレーズを使ってきた。
アナログで存在するものをデジタル化して集め、そのデータを分析することで、そこに新たなビジネスが生まれる。これまでも「検索のキーワード」、「商品の購買履歴」、「人の行動履歴」などが、それらを集めるプラットフォームをもった企業によって収集、データ化され、別の巨大ビジネスの源となってきた。
あちこちに生息する生物も同様。バイオームはアプリを無料で提供しており、現在88万ダウンロードにまで広がっている。ユーザーは、『ポケモンGO』と同じく、コレクションを増やす感覚で動植物のデータを楽しみながら集めてくれる。それをデジタルデータにして集積すれば、その先に新たなビジネスが生まれる。バイオームが目指すのは「生きものデータのプラットフォーム」だ。
いきものコレクションの先にあるビジネス
ただこの説明で、ピンとくる人は、6年前の創業時にはほとんどいなかったという。ところが、ここ数年で状況は変わってきた。
「最近は、(ビジネスへの評価は)理解の度合いによるかなと感じてきました。今のネイチャーポジティブの流れをよく理解している方にとっては『めちゃくちゃ面白いね』となる一方で、まだピンときにくい方もいます。背景知識の差が出て、評価がわかれるって感じですね」
近い将来日本でも、企業活動が生物多様性にどのような影響を与えているのかを開示することが求められるようになる。また、自治体や企業が自ら管理、保有するエリアで自然を守り、回復する取組みを進めることも必要となる。どんな情報を開示すればよいのか、どの場所をどう保全すればよいのか、全てにおいて生物多様性に関する知識やそのエリアのデータが必要だ。
こうした自治体や企業が必要とするデータを、効率的に集める工夫がバイオームのアプリには備わっている。「クエスト」という機能だ。特定の時期・エリアでテーマに沿った生きものを見つけて投稿するという「宝探しゲーム」的な機能で、例えばこれまでに「土佐の植物博士クエスト」や「あだち(足立区)生きもの図鑑をつくろう!」など、数多くのクエストが組まれてきた。これが自治体、企業のために特定のエリアのデータの数や精度を上げる仕組みとして利用できる。
データを利用した具体的なビジネスとしては、自治体が生物多様性の地域戦略を考える際のリストやデータ提供などの政策支援。さらには外来種の防除や、希少種保全を行う際の基礎データ提供など。民間企業との間では、TNFD(自然関連財務情報開示タスクフォース)の開示支援や自然共生サイト認定支援などといったように多岐にわたる。
「これはやらない」という一線
エコツアーや有機農法の効果測定などビジネスのフィールドを拡大しつつあるバイオームだが、「これはやらない」ということについて藤木さんは、はっきりとした一線を引いている。
「僕は環境保全につながること以外は絶対やらないようにしています。でないと、(会社を)作った意味がわからなくなるので。なので、どんな案件であれ『環境保全に資するかどうか』という軸だけは絶対に見ていますし、(その判断基準で)断った案件も少なからずあるんです」
環境破壊につながる開発計画である場合には、どうすれば環境保全と開発が両立できるのかのアドバイスをすることもあるという。地域のデータを持っている同社だからこそ、知識とデータに基づき的確な提案ができる。
生物多様性スタートアップの難しさ
インタビューを進めている中で、あらためて感じたのは生物多様性に関するビジネスには、当たり前のことだが、生物や生態系に関する豊富な知識が必要だということだ。
「生態学的な解釈ができるとか、そういったものがないと。やっぱり最終的には“解釈”を売ることも多いんですよ」と藤木さんも言っていたが、開示資料を作成するといった専門的な業務には専門知識が欠かせないのはもちろんのこと、アプリ開発やサービスの仕様を定める場合においても「生物の同定精度を上げるには観測場所や日時の情報が必要」であることや、「希少生物の生息場所はアプリ内で公開しない設定にする」など、研究者としての知識や経験が役立つ場面が多い。
生物多様性のスタートアップをあらたに起業する難しさは、このあたりにあるのではないだろうか。バイオーム創業者の藤木さんはその方面(生物生態系)の専門家からIT方面(アプリ開発など)に向かったが、IT方面から生物多様性の方に入ってくると、アプリソフトの開発はできても、いざ仕事を始めてみると専門知識の欠如で、顧客の要望に応えられず早い段階でつまずいてしまい、ビジネスチャンスの芽を発見できないで終わってしまう可能性がある。
ということで、難しさはあるがこのフィールドは、まだまだこれからだ。藤木さんももっと多くのスタートアップがこの分野にも登場してほしいと願っている。
「マーケットは大きくなると思います。スタートアップもいっぱい出てくるでしょう。うちはデータプラットフォーマーのポジションですけど、サプライチェーンの可視化に必要な生物以外のデータとかも必要ですね。あと当社が弱い海(の生態系のデータ)も必要。環境DNA使って(海の調査する)とか、いろんなアプローチがあり実際そういう動きも出ています」
バイオームも現在は日本国内にとどまっているサービス対象エリアを東南アジア方面へと近いうちに拡大する予定だ。「生態系には国境はないので。実際のところ途上国のデータの方がニーズがあるんです。(企業も)自分たちの原材料調達地の状況を知りたいけどデータがない。そういうデータがしっかり集まる仕組みができたら、もっと世の中の役に立つかなと」
創業以来6年あまり、「生物多様性」「ネイチャーポジティブ」という言葉が世に知られるようになった今年、バイオームのビジネスにも追い風が感じられるようになってきた。
「今すごくそういう知識が広がっているので、その後ろから追いかけていくと、知識を持った企業はみんな乗ってくる可能性があるなと。もっと社会に浸透していけば、うちとしても社会的背景や前提知識の共有にかけるコミュニケーションコストも少なくて済むし、もうちょっとできることが増えていくだろうと思います」
藤木さんのようなファーストペンギンの労が報われ、環境保全がビジネスとなることが明確になれば、あとに続くスタートアップも次々と登場するようになるだろう。











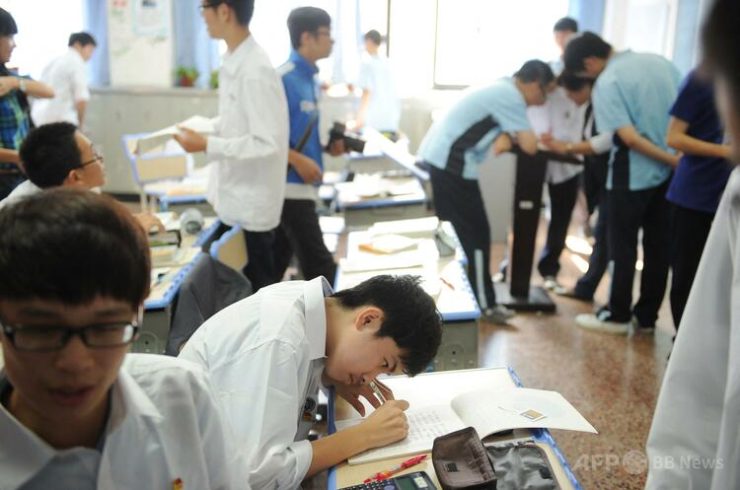


 スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs
スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs