造園と生物・生態学との出会い 造園ユニット「veig」が仕掛ける造園イノベーション

とあるプロジェクトの現場にて 西尾耀輔さん(左)と片野晃輔さん(撮影:田川紘輝 ©nando inc.)
「造園」とは、庭を作る仕事だ。庭を作るのは、植木屋、庭師など造園業に携わる人や企業で、個人宅から公園まで大小様々な庭を手掛けている。庭園には、多くの木や草花などの生物があるが、意外なことに庭を作る造園業の人たちと、植物や生態系を扱う研究者との間にはほとんど交流が無いという。
庭を作る人と研究者が協同すると、どのようなイノベーションが起きるのか。今回のインタビューは、「造園+生物・生態学」で実際にプロジェクトを手掛ける2人に話を聞いた。
* * *
富山県小矢部市に本社がある造園業の株式会社越路ガーデンの3代目で、同社東京オフィスの所長西尾耀輔さんが一方の主役。相方は以前、当媒体にMITでの研究生活などをレポートしてくれた在野の生物学者(ワイルド・サイエンティスト)の片野晃輔さんだ。2人は「veig(ヴェイグ:名称の由来は文末参照)」という造園ユニットを組み、これまでにはなかった役割と形をもった庭作りを始めている。
MIT、CSLそして造園への道のり
――まずは片野さんだが、MITで合成生物学の研究者の道を歩んでいたが、それがどのようにして庭造りにたどり着いたのだろうか。――
片野晃輔(以下、片野):MITには、僕が19歳あたりからで、今年は26歳になるのでもう7年前くらいですね。まずは数ヶ月行ってみて、その後1年とちょっと在籍していました。帰ってきたのはコロナが蔓延する前です。
MITのメディアラボで、シンセティック・ニューロバイオロジー(Synthetic Neuro Biology合成神経生物学)グループで神経系の研究したり、コミュニティー・バイオテクノロジーグループで、技術の民主化とか。周りの人たちに研究(の内容や成果)を伝えるのは面白かったのですけど、もう少し自分がフィールドに出て話をした方が説得力もあるし、研究室にこもりながらそういう話をしてもリアリティがないなと。タコツボ化してきたなって感じて、若いからやり直したいなと思って。
それで別の研究室を探し始めて、結構いろんなところ探して、ドイツの林業だったり、アメリカの大規模農業とか色々あるのですけど、ちょっと農業に寄り過ぎて、それもまたタコツボ化するのだろうなと思ったので。
それでもうちょっと“広め”のところ探していたら、ソニーCSL(Sony Computer Science Laboratories, Inc.以下、CSL)を紹介してもらうことができて。(CSLのCEO)北野宏明さんにメール送ったらすぐ返事いただいて「じゃあCSL 来てよ」みたいな。ちょうど帰国してすぐで、行ってみたら研究員全員が集まったホールで「じゃあプレゼントお願い」ということになって。「日本語でいいですか」って言ったら、「絶対ダメだよ。CSLで日本語通じないから」(笑)。
CSLでは、協生農法・シネコカルチャーを研究、実践していた舩橋真俊さんに紹介してもらうつもりだったんですけど、舩橋さんその時はアフリカに行っていて、舩橋さんからは「帰国したら会おうよ」って。お会いしてプレゼンしたら「いいね、年末年始からちょっと来てみてよ」。
――こうしてCSLに所属し、同時に舩橋氏が代表理事を務める一般社団法人シネコカルチャーも兼務。市民科学寄りの業務を担当しつつ、“まちづくり”などにも関わるようになった。しかし、組織には組織の目的と手法がある。舩橋氏から学んだことは多くかつ有益で、さらにシネコカルチャーにも大いに啓発され、視野も広がったが、方向性や手法の点で組織の一員としてやることの窮屈さも感じた。また、これまでは「MIT」「ソニー」といった“箔つき”で過ごしてきたが、「本当に自分で何ができるかをもう1回見直さなきゃいけない」と感じていた。そして、まちづくりにしろ、なんにしろ「もう少し世の中の人を巻き込んでやっていきたい。“コラボレーション”と言ったらちょっと軽く聞こえるかもしれないですけど、共同でやっていくのがいいな」(片野さん)という大前提があるので、これを実現したいという強い思いもあった。――
片野:舩橋さんには、「本当に今辞めるのか」と言われたのですけど、「今辞めて、来月喰える算段ついてないけど辞めます。辞めたら多分焦るんで、頑張れると思うので」。研究者が外に出て食べていくのは結構無理な話というか、日本だと次に行くあてがないと辞める人はいないので。僕も不安でしたけど、独立してからは、地方の大学などとコラボして、僕が研究のプロデュースのようなことやっていました。「種(シーズ)」の部分を僕がいくつか持っておいて、人と出会う毎に、相手の様子見ながらそれを提供してプロジェクト化していくのですね。人にいっぱい会って、武者修行的にやっていました。結局、高校の頃もそうやっていて、卒業してからもスタートアップを手伝ったりしてお金もらってたので、あの頃と同じようにやればいいわけだと。より経験は積んでいるので、やりやすくなっているはずだし。しばらくはそうしながら何やろうかをじっくり考えてみようと。
――研究者として、論文を書いてアカデミックの分野でも貢献したいという気持ちはある。一方でMIT時代の体験から、論文至上主義的な考え方に疑問もあった。MIT在籍時、片野さんが所属していた研究室には、論文製造機のように次から次へと論文を生み出す研究者が揃っていた。それはまさに競争で、ついていくにはアスリートのような強靭さが必要だった。「そういうところで勉強させてもらえて、そこで腕を磨けたので良かったのですけど、でも『ここで何を磨いているのだろう?』って気持ちにもなりました」(片野さん)。CSLで生態系のこと学んで、そこを辞めた後、どういう経緯でランドスケープや造園につながっていったのだろうか。――
片野:ランドスケープの分野は、CSL時代にも関わったことがありました。でも、デベロッパーさんや行政と一緒にまちづくりやっていると、実のない話が多すぎると思ったのです。すぐサウナ作るし、木を切ってホテル作るし。一面芝生の広場を作っておいておしまい。結局景色は消えてるなみたいな。多くの場合「生態系」って言葉の魅力だけ利用して、「生態システム(系)」を見てないなって。なぜかなと考えてみると、どこにでも生態系はあるけど気づかない。だからといって「(生態系を知るために)一緒に森歩きましょうよ!」っていうのは、ちょっと不思議な誘いじゃないですか、時間も限りあるし。そうなると、生態系を人に伝えるには、もう少し手近な場所で話をした方が良いのじゃないかと。人は都市に集まってくるわけで、街なかの緑を見て話すのが一番てっとり早いですよね。それなら街なかの緑地を(生物や生態系が学べるように)僕の知見を活かしてつくればいいわけです。でも、見栄えが悪くて、面白くないものだったら誰も興味持ってくれない。だからこそ体験は大事というか、人がどう思うかってことは大事で、そこは絶対に妥協したくないなって思ってました。
造園の「設計」「施工」「管理」と大学時代の学び
――次に西尾さんに造園業とはどんな仕事なのか、また、どういった方法で庭造りを学んできたのかを聞いてみた。さらに三代目の跡継ぎとして、造園業を選ぶことに迷いはなかったのだろうかということも。――
西尾耀輔(以下、西尾):造園は「設計」「施工」と「管理」が主な仕事内容になります。設計監修というのもあって「監修」というのはアドバイスですね。住宅から店舗、もうちょっと広いランドスケープって言われる公園だとかホテルのような大きな開発のアドバイスや設計協力もやります。施工自体も、僕は主に自分が設計した空間の施工です。富山の本社部隊は、ゼネコンさんから受けて、病院の周りを全部とか、新しい庁舎の周りをやりますといった大きな工事も手掛けます。街路樹の管理、河川の土手のようないわゆる行政管理の大きな仕事から、町を構成する一つひとつの家、もっと小さいプランターレベルまで、広く仕事させていただいているのが今のスタイルです。
造園設計は、お客さんにヒアリングをし、どういう景色や場所が好きだといった話から始まって、適切な樹種を選定した上で、「石はこの地域に産出するのはこれ」とか、そういった提案をしながら構成していくのが設計の簡単な流れになります。それを作るのが施工で、管理というのは、年に1、2回程度なのですけど成長した木を整えていく。設計、施工の時に思い描いた風景やお客さんと考えたイメージが長年楽しめるように、「この木は伸ばしていいけど、この木はこれくらいで」というのをお客さんと決めて手入れしていきます。
(造園の道に入るにあたって)おじいちゃん子だったので、祖父が作った会社を潰すわけにはいかんかなって。まあ、東京農業大学には、半強制入学だったので(笑)。2年生ぐらいまでは、植物の種類も知らないし、身が入ってなかった。でも、かっこいい先輩を見つけまして。その先輩は仕事に対する向き合い方がすごく誠実な方で、植物の生産・卸しをメインにやっている方なので、例えば枝が1本も折れないように気をつけて養生してから運び出すとか。こんなふうに植物や仕事に向き合えるっていうのはすごいことなんかなと。自分も先輩と同じようにしたいし、「(造園業を)継ぐというのではなく、ちゃんと自分で造園の仕事がやりたい」と思って勉強し始めたのは大学2年の終わり頃です。
東京農業大学の造園科学科は、「造園」って名前がついているすごく特殊な学科で、日本中から造園屋の息子や娘とかが集まってくる学科です。そこでは広くきっかけを与えるような授業が多く、植物生理学の研究室から、日本庭園の実測修復保存、この時代はこういう材料が使われて、今はこうというような材料学。ランドスケープと言われる広い公共空間、広い敷地のデザインを学ぶランドスケープデザイン、自然公園などの整備に取り組む景観学などもあります。その中から気になったところを掘り下げていくみたいなところで、僕はほとんど全てに興味があり、なんでもやりたかった。特に日本庭園とかかっこいいなと思って、先生と二人三脚で古い庭園の実測と調査と保存をやらせていただいたりだとか。卒業論文では、牧場のランドスケープの設計で卒業をしているのですけれども。
学校では机の上で勉強しながら、僕は施工もやりたかったので、大学卒業してからだともう遅いなと思って、造園屋さんでアルバイトしてました。アルバイト代はほとんど交通費に使って、日本中の植木屋さんに会いに行って、話を聞いて回りました。植木屋さんは優しいですよ。「東京農大の西尾といいます。こういう思いで勉強してます。是非、現場見学させてください」ってお願いすると、植木屋のおっちゃんたちは、そういう若者大好きなわけなんです。「一泊で来いよ。夜飲むぞ」という感じで。
植木屋さんからは、「この地域では、この植物のことこういう名前で呼んでるんだ」といったローカルな知識から、その人の仕事に対する思いとか。そういうものも見て、学ばせていただきました。木の切り方も 関東と関西で違いますし、東北も違います。(地域が違うと)成長の仕方とか土が違うのです。東京だけで仕事をやってたら、関西で仕事もらった時、そこで苦労する。僕は、まだまだ経験値が足りないですが、日本中のそういう現場を見て回ったというのがあるので、今になって、いろんな県からお仕事いただいた時にそれが活きてくるというのはあります。
同い年の2人の出会い・共通点
――実は2人は偶然にも同い年なのだが、共通なのは年齢だけで、これまで全く別の世界で過ごしてきた。いったいどういったきっかけで知り合い、一緒に仕事をすることになったのだろうか?――
片野:CSL辞めた後に、「ランドスケープに興味があるなら土木バイトやってみたら」と知人に言われ手伝ってみたら、この延長線上に造園があるのだなって。そうすると造園のプロとやった方がいいなと感じて。最初はランドスケープアーキテクトのような大きめのエリアを手掛ける人を探して、何人か話しをしたのですけど、「あのあたりに木を植えておこうよ」という程度の粒度で、ふわふわした感じで。
僕が話したかったのは、「誰に何を伝えるのか」、「本当に伝わっているのか」といった体験の話なのですけど、ランドスケープアーキテクト規模の仕事を手掛ける人は、そこまで細かい話はしないし、そういう仕事の仕方じゃないんだなっていうのが分かって。だったらもうちょっとスケールを絞って、大きいのもできるけど、個人宅の庭もやりますというのは「庭師」だなあって。
いろんな庭師がいたのですけど、西尾さんとは一番話ができて、話も合ったんです。西尾さんは「それすごく似たこと感じます。『環境にいい』とか『庭の文脈でいい』とか言うことはあっても、その前に話すべきこと、感じるべきことはいっぱいあるよね。まず空間が面白くて、だからこそ話せる。そういう場を作りたい」と。それで「一緒にできたらいいですね」という感じで。ユニットに。
――話を聞くと、年齢以外にも2人には似たところがあるのがわかる。それは、知りたいことがあれば、その分野のスペシャリストを探して遠慮なくその人に話を聞くこと。年の離れた知らない人、それもその分野の著名人にアプローチすることに躊躇したことはないかと質問したが、2人は声をあわせて「全然ないです」と即答。話を聞くにあたって、西尾さんは「著書が出ている人なら読んでから訪ねます。(実際に会って、仕事を見て)何が書いてある通りで、何が違っているのかがわかるので。仮説と検証ですね」と話してくれた。また、2人は適度に疑り深いところも似ているらしい。――
片野:バズワード的に「環境」「生態系」が使われているけど、それを疑ってみている人が少ない。そういったところで疑いの目を持つと、「やっても無駄でしょ」とかなるのですが。でも、そこから先に「いやでもできることはあるよね」みたいなちょっとトリッキーな人を僕が求めるらしいです(笑)
西尾:僕も「ほんまにと?」とだいたいのことは疑ったりしてしまいます……。
片野:僕が何言っても「ほんとに?」というくらいで丁度いいのですよ。集中しすぎて熱くなって判断を間違うことも多いので。 “土台を崩すような会話”ができるのはいいなっていう。
西尾:同業者だったら疑わないとことかあるので、業界内の常識とか、慣れちゃって、疑うことを忘れるというか。やっぱり“ツンツン”してもらえるのは、新しい発見とかにつながるので。
ユニットであることのメリット
――通常の庭造りはもちろん西尾さん独りでも完結できる。では片野さんが加わるメリットは何なのか?造園のオープンイノベーションはどのような価値を生むのだろうか。――
西尾:僕ら(造園業者)は、空間としての美しさとか、使いやすさという「機能」については、これまでも考えてきたのですけど、「機能」ってそれだけじゃない、というのは彼から教えてもらって。(植物や生態系の機能として)「食べる事ができる」とか「鳥を呼べば、虫を食べてもらえる」「その植物の組み合わせはいい作用がある」とか。これまでの造園では、この木を合わせたらかっこいいなとか、花の咲く時期のバランスなどは考えたりはするのですけど、「受粉のこと考えて」とかあまりやらない。彼から教えてもらって「複層的」に植栽の配置を考えるようになりましたね。
片野:すごく「草本」を使うようになりましたよね。
西尾:ただの美しい草だと思っていたら、「食べられる」ってなると「じゃあ道の近くに植えてあげようかな」とか。デザインにも影響してきて、美しさを考えた配置と、そこに機能が重なった配置。いろんなフィルターが重なってすごい複層的になる。

片野:そうなると、話せることがたくさんあるという。結果的に誰が来ても、どんな話でも無限にできる庭が理想としているところで。面白いから、実がなる木を見て「あっレモンだ」となる。僕たちから言うのでではなく、鑑賞者が「なにこれって」って勝手に面白がってくれる。
――片野さんがCSL時代に舩橋さんから学んだ環境の「見立て」も役立っているという。例えば博物館内で生態系を再現する際、展示室は「暗がりで、風がなく、光が弱い。森の暗がりに似ている」と見立てる。従来の造園家目線だと「暗いので耐陰性のある植物、乾いているので乾燥にも強いもの」となる。だがそこを「森の奥の方 林床だ」と見立てると、そこには森の奥深くの林床の生態系を再現すればいい。植物ベースで考えるのではなく、景色をベースに考えられるというのは、「とてもいい考えをもらった。造園家としてのアドバンテージになる」(西尾さん)。ところでさらなる造園イノベーションのためには、他にどんな専門性を持った人材の参加が求められるのか。これまた、接点がなかったことが意外なほど近く思える分野の名前が上がった。――
片野:森林系、林業関係の設計者が面白いなと。林業の現場に近い人たちにお会いする機会あるのですけど、間伐とかはわかるけど、森をどうして行こうかってプランナーみたいな設計の思想がある人はレアですね。
西尾:林業って、長期的に50年とか80年とか見据えてやるプロジェクトなので。「森をつくりたい」という人は多いのですが、造園だけじゃ森は作れないんですね。森つくるには、自分で樹種を選び、植物をばっと植えて、「これが森です」ってわけにはいかなくて、50年後を考えた配置というのが必要になります。作りたい森の姿を実現するためのチームが必要かなとは思ってますね。
片野:生物学と造園があんまり交わってなかったのと同じぐらい、林業と造園は距離がある。生態系という意味では扱うものは同じなのにスケールと時間が違うのです。解像度が違うので、同一の空間で複層的に相乗りしても成立するはずで、見てる時間とか違うので、(林業の人は)「じゃあ私は大きいとこ設計するので、その中の細々したところは造園の人達で設てください」で、生態学者はそれを見て何がこの場所できるかとかを情報提供するっていう組み合わせかなって。
西尾:森ってすぐにはできないじゃないですか。でもお客さんはすぐ欲しがる。森林設計できる人が入れば、今は造園家が作って庭として見られる景色にしておき、50年後に森として成立する時限装置というか仕掛けを林業家の視座で作っておけば、僕らは見られないかもしれないですが、子供や孫の代にそこは森として成熟する。明治神宮の森なんかは先人たちが仕掛けた装置ですね。生態系とか森とかを考えるきっかけになる存在になっている。
片野:素晴らしい空間は教材に近いですね。論文の類に近い。多面的に引用したくなるような。
他にも建築家やデザイナー、グリーンファイナンス関連の実務者など、プロジェクトに参加してもらうことで庭造りの可能性が広がる職種、人材はいろいろとあるようだ。
veigのプロジェクトでは、今ある何かを変えようとする人、それも大きく変えようとする人がクライアントになる事が多いという。また、veigの仕事のプロセスはユニークで、お客さんには共同設計者として、「あれが好き」「これが見たい」とたくさん話してもらい、それを取り入れ形にして庭や風景にする。その庭や風景を目にするとまたいろんな話がしたくなる。
会いたい人、参加して欲しい人の話は次の発言で締めくくられた。
片野:お客さん普通に待ってます。僕らと喋りながら作りたい人。
西尾:庭づくりや森づくりについて楽しく一緒に考えたい人。
* * *
Veig(ベイグ)=造園家西尾耀輔と生物学者片野晃輔のユニット。「ぼやけている」、「曖昧な」という意味の(vague)の発音記号「veig」が名前の由来。本業あってのユニットなので、妥協はせずクライアントと会話を重ね、「情報量も植物の種類も多め」の庭を作りあげている。(連絡先はgeneral @ veig.jpまで)


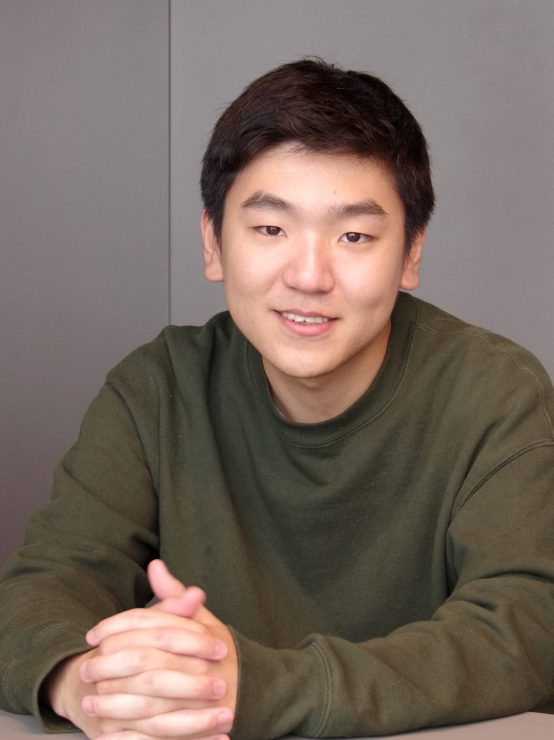











 スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs
スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs