「大学に行かずにバイオの研究者になる」19歳の挑戦

惜しくも29連勝でストップしてしまったが、将棋の藤井四段の活躍が注目を集めたのは、連勝記録の更新ということもさることながら、それが14歳、中学2年生という若さで成し遂げられたことも大きい。
藤井四段の落ち着いた受け答えの様子などを見ていると、若くても立派な態度に感心し、どのように育てればこういった人材が育つのかと、親世代は関心を持つだろう。また、同年代の人は「いつ」「どうして」「どんなきっかけで」この道に進む決断をしたのか興味があることだろう。
将棋とは分野は異なるが、バイオの分野にも若くして、その才能を発揮しつつある人物がいる。すでに何度かこのDG Lab Hausにも、MITメディアラボでの研究生活の様子について寄稿してくれているが、その筆者である片野晃輔さんだ。片野さんは現在19歳。高校卒業後、大学には進学せず、研究者の道を選んだ。この6月まで3カ月間MITメディアラボで研究生活を行なっていた。中学時代からアレルギーのIgE抗体産生やガン細胞の発生のメカニズムなどに興味をもち、中学3年の時にオジギソウのバイオセンサーに関する研究で木原こども科学賞の優秀賞を受賞した。高校進学時には、すでに通常の学生生活ではなく、研究者として生活を送ることを決意し、現在に至っている。
* * *
片野さんの出身は、新潟県新潟市中央区。市の中心部で、映画館も近所にありながら、すぐ裏には日本海に注ぐ大河、信濃川が滔々と流れる様子を見ることができる場所だ。こども時代から映画を見る機会が多く、洋画や少し古い(19歳の片野さんにとって)「ガンダム(宇宙世紀シリーズ)」や北野武監督作品などの日本映画が好きだという。小学校時代はプラモデルやアニメなどが好きなごく普通の小学生だった。
中学校入学後、最初に選んだ部活動は陸上部。「走ると気持ち良さそうだったから」という動機だったが、雰囲気に馴染めず、ちょうど部室が隣にあった理科部に入り直し、それがこの道に入るきっかけとなった。そこで最初に取り組んだのは、クーラーがない部室を冷却する装置を自作することだった。この装置は送風に自転車空気ポンプを使う仕組みのため、空気を送るには大汗をかいてポンプを忙しく動かす必要があった。そのため、暑さは解消されず失敗に終わった。
当時は中学生らしく、このように動きのあるものに興味があったのだが、親族のガン罹患がきっかけに、遺伝子などバイオ分野へと興味が移った。ガンについて調べているうちに、治療方法より、ガン細胞が発生するメカニズムが面白くなり「がん?なんだこれは?面白いな!」と深入りしていった。
多くの人は、がんについての初歩的な知識や治療方法などを理解すれば、そこで探求は一旦停止することが多いが、片野さんの場合は違った。より根源的な疑問を解くためには、専門書から日本語の論文、さらに英語の論文を読むようになったという。
このように専門的な文献にアクセスできたのは、時代の恩恵だろう。かつては中学生が学術論文を入手するのは難しかったが、近年、世界中の各種論文がインターネットを通じて容易に入手できるようになった。こうした環境が、片野さんのような若い研究者が生まれる背景になっているのだろう。
ところで、片野さんの興味は、ガンにとどまることなく、その後も広がっていく。中学時代に木原こども科学賞を受賞したのは、オジギソウの研究だが、この研究のきっかけがまた面白い。映画「スターウォーズ」のとある場面で見た模様がホログラムのように変幻するテーブルを再現したくなった。ハプティクス(haptics)的なものを導入するには植物のセンサーが使えるかなと考え、食虫植物やオジギソウのセンサー機能に注目し、その研究結果を応募したところ受賞につながったという。
さらに、木原こども科学賞受賞時に審査委員から『理系の子』(ジュディ・ダットン著 文藝春秋刊)というインテル国際学生科学技術フェア(ISEF)に参加する学生たちのドキュメント本を紹介され、これに大きな感銘を受けた。これがきっかけとなり、科学への情熱の「リミッターを解除」したのだという。
リミッターが解除されたためか、研究に身を入れすぎて、高校受験の勉強がおろそかになり志望校には落ちてしまった。結局、ごく普通の高校に入ることになったが、そこでも研究活動に専念したかったので、入学後すぐに教員にプレゼンテーションした。ところがまったく理解されず、普通に高校生活を過ごすように言われた。また、中学時代はあまり周囲と異なることをしているという意識がなかったのだが、高校に入ってからは「論文ばっか読んでいてキモイな」などと言われショックを受けた。本人曰く「迷いの時期」だったということで、普通に大学行くべきかなどと少し考えたこともあるという。しかし、前述の『理系の子』を心の励みにして、研究機関や大学など30以上のラボに連絡をとり、自分のやりたい研究内容を説明し、高校生である自分に協力してくれる研究者や、受け入れてくれるラボを探し当てたのは、驚くべき行動力だ。
その後は、そうした組織や応援してくれる研究者の助言を得ながら、高校在学中も エピジェネティクスの研究などを進めてきたという片野さん。自身が大学に行っていないからといって、大学進学に否定的かというと、必ずしもそうではなく、自身の真似をしたいという後輩には、再考をすることをすすめているらしい。
大学に行かなかったメリットとデメリットを問うてみたところ「時間があるので、多くの人に会って話をすることができるし、研究にも時間がさける。けれど、その分自分を追い込まないと研究が前に進まない」。良くも悪くも与えられた時間の過ごし方次第だということだ。実際、学歴だけを見ると高校卒業となるので、留学の資格審査などでは不利な扱いをうけてしまうこともあるようだ。

情報工学等を扱うSTATAセンターはFrank Gehryが設計した建築物(写真は全てRikuo Hasegawa氏からの提供)
まだまだ、大きな実績はおろか、専門分野ですといえる分野も定まっていないという片野さんだが、この春からの短いMITメディアラボでの研究生活で、さらに大きな経験をつんだようだ。同ラボではエド・ボイデン氏が主宰するSynthetic Neurobiologyのグループに研究者として所属。これまで扱ってきた分野と異なる分野ながら、研究所のボスであるエド・ボイデン氏の人物とバックグランドに興味があり、その考え方を学びたいのだという。そんなボスとの間でも、自分が実施したいプロジェクトを巡って大論争中だとか。周囲もハラハラするようなボスからの「完全NG」をくらうも、めげずに、研究室から吸収すべきものはしっかり得ようとしているようだ。
* * *
余談ながら、異国の地でたくましく、また楽しげに研究生活を過ごしてきた片野さん。さぞかし英語も堪能なのかと思いきや「英語には苦労してます」とのこと。短期のオーストラリア留学経験はあるものの、特に英語が得意だったわけでもないという。英語の論文を読んでいたので、専門分野の単語はわかるものの、日常の会話について、はじめは苦労したようだ。研究グループの国籍は多様で、いろんな訛りの英語があるらしく、最初に研究仲間のロシア人が英語で話しかけてきたときは「全く理解できず驚いた(笑)」。
日系アメリカ人のルームメイトに教えてもらうなど、こちらは人並みに苦労があった、という話を聞くと「それなら私も大丈夫」と勇気をもらった気になる人も多いだろう。
* * *
ラボでの食べ物の争奪戦や、MITのいたずら文化を楽しむことなどを通して、英語とボストンでの研究生活馴染んでいく様子は、これまで片野さんが寄稿してくれたコラムで垣間見ることができるので、そちらもぜひご一読を!








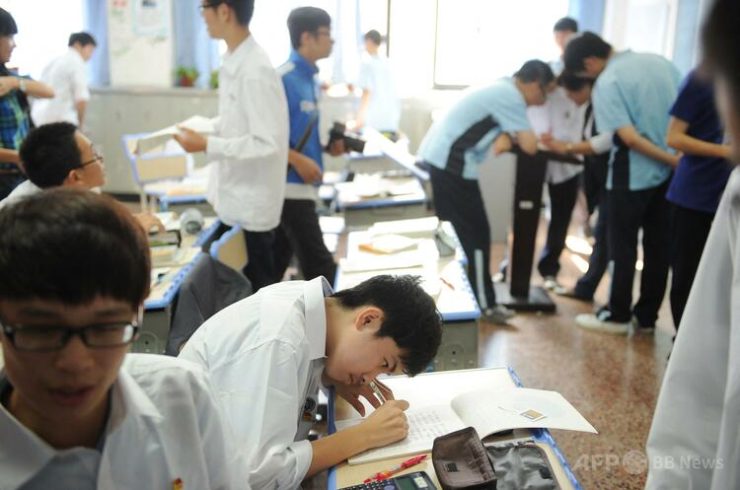


 スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs
スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs