【日本人が知らない 、世界のスゴいスタートアップ Vol.12】AIが「透明化」するインフルエンサー・マーケティング

AIが「透明化」するインフルエンサー・マーケティング(イメージ図)
連載「日本人が知らない、世界のスゴいスタートアップ」では、海外のベンチャー投資家やジャーナリストの視点で、日本国内からでは気が付きにくい、世界の最新スタートアップ事情、テック・トレンド、ユニークな企業を紹介していきます。今回のテーマは、「AI(人工知能)で進化するインフルエンサー・マーケティング」です。(聞き手・執筆:高口康太)
* * *
ユーチューバーやインスタグラマーを起用した、インフルエンサー・マーケティングが存在感を高めている。私自身もインフルエンサーのオススメどおりの商品を買うことが増えてきた。2023年には、日本でもインフルエンサー・マーケティングに費やされる費用が741億円に達したとの推計もある(サイバー・バズ/デジタルインファクト調べによる予測値)。2020年の332億円から倍増以上という急成長で、もはや立派な広告チャネルとなっているのだが、広告の出し手にとっては課題もあるという。
それはどのクリエイターを起用するのが効果的なのか、適正な広告料はいくらなのかをリサーチするのが難しいこと。そのあたりをサポートするサービスもあるが、広告を出す側のノウハウ不足もあり、無駄な出費も多いという。
インフルエンサー・マーケティングをどう透明化、効率化していくのか。AIの力を借りて、この課題に取り組むユニークな台湾企業があると、世界のスタートアップ事情に詳しい台湾の投資家、マット・チェン氏が紹介してくれた。
鄭博仁(マット・チェン、Matt Cheng) ベンチャーキャピタル・心元資本(チェルビック・ベンチャーズ)の創業パートナー。創業初期をサポートするエンジェル投資の専門家として、物流テックのFlexport、後払いサービスのPaidyなど、これまでに15社ものユニコーン企業に投資してきた。元テニスプレーヤーから連続起業家に転身。ジョインしたティエング・インタラクティブ・ホールディングス、91APPは上場し、イグジットを果たしている。
ディープフェイクとインフルエンサー
――インフルエンサー・マーケティングが流行しています。
マット・チェン(以下、M):そうですね。しかも、さらなる追い風もあります。グーグルのウェブブラウザー「Chrome」でのサードパーティ・クッキー廃止も目前に迫っています。廃止されると、広告効果の高いリターゲィング広告(過去に自社サイトを訪問したユーザーに対して、別のサイト上でも自社広告を表示する手法)がやりづらくなり、広告効果が低下します。ウェブ広告業界に与える影響の大きさから再三にわたって延期されていますが、廃止という方針に変わりはありません。となると、相対的にインフルエンサー・マーケティングの優位性が拡大します。
サードパーティ・クッキー廃止に加え、AIという新たなテクノロジーがインフルエンサー・マーケティングをさらに強化されるトレンドが見えてきました。
――確かに、生成AIを使うとステルス広告のような口コミ投稿を簡単に作れちゃいます(笑)。ニューヨークタイムズが取りあげていましたが、中国では、実在のロシア人女性の顔を使ったディープフェイクで商品を宣伝したり、「中国の男はロシア人を妻にするべき」とお愛想をいったりというディープフェイク・インフルエンサーが増えているのだとか。
M:文章や画像だけではなく、動画ですらAIが簡単に生成できます。すでに、多くのスタートアップがAI技術をインフルエンサー・マーケティングの分野に応用し始めています。
今年3月、ツイッター(現「X」)である動画が話題となりました。自動車の車内にいる女性がウェットティッシュの宣伝をしているという不思議な内容ですが、実はこの動画、AIによって作られたものだったのです。
Arcads.aiという企業のサービスで作られたものですが、彼らの手法はユニークです。まず俳優によって演じられた、多くのパターンの映像を用意しています。クライアントはその映像を選び、話させたいテキストを入力すると、機械音声とは思えないような流暢な音声でそのテキストの内容をしゃべり、また口の動きも話している内容とシンクします。
――簡単な操作で口コミ風の宣伝動画が作れてしまうわけですね。同社の公式サイトを見ると、彼らのサービスのメリットが紹介されています。低価格でしかもあっという間に動画が作成できることというのはまあ予想できますが、「クリエイターとのコミュニケーションから解放される」のもメリットと言われるとちょっとドキッとしました。確かにメールや電話って面倒ですが……。
M:ただ、こうしたAIによる直接的なコンテンツ生成というシナリオは厳しいのではないか、というのが私の見立てです。確かに安く、大量にコンテンツを作れるという意味では役立ちますが、「真実性」と「信頼」という、インフルエンサー・マーケティングの根本的な価値から乖離しています。AIによるレビューだと消費者が知れば、マーケティングの効果は大きく減少するでしょうし、下手をすれば紹介した商品やブランドの評価を傷つけることもありえます。
――生身の人間が話していることがインフルエンサー・マーケティングの売り、だとすると、AIの活用はむしろ逆効果というわけですね。
M:AIによるコンテンツ生成は負の側面が大きいと見ていますが、AIには別の用途もあります。それは既存のマーケティングの精度と効率性の向上です。チェルビックキャピタルが出資している台湾のスタートアップ、iKala(アイカラ)はこのアプローチの代表格であり、きわめてユニークなAIツールを開発しています。
ビッグデータの整理はAIの得意分野
M:iKalaは2011年の創業。初期の事業はクラウドソリューションですが、2018年にインフルエンサー・マーケティング市場に事業範囲を広げます。同社のインフルエンサー仲介プラットフォーム「KOL Rader」には、フェイスブック、インスタグラム、ユーチューブ、ティックトック、X(旧ツイッター)の300万人以上のインフルエンサー・プロフィールが登録されています。カバーしている国、地域は日本、台湾、韓国、マレーシア、タイ、ベトナム、シンガポール、香港です。
広告クライアントはこのサービスを使って、自社の製品やサービスの広告を依頼するのに最適な相手を選び出すことができ、インフルエンサーとの連絡、契約、支払い、そして広告後の効果測定レポートの作成までもワンストップで手がけています。すでに5万社以上が利用しているプラットフォームとなっています。
――300万人!その中から自社に最適なインフルエンサーを探し出すのは根気が要る作業ですね。
M:もともとインフルエンサー・マーケティングでは誰に依頼するかを調べるリサーチが、もっとも時間のかかる作業でした。フォロワー数が多い人、視聴回数が多い人に頼めばそれでOKという単純な話ではありません。いかに多くのファンを抱えていようとも、商品との相性が悪かったら効果は上がらないので。どのようなインフルエンサーなのか、どんなコンテンツを作っているのか、ファンのプロファイル、過去の広告案件の実績を加味して慎重に選択する必要があります。
――そういえば、私も以前、Xアカウントに広告案件の依頼が来たことがありましたが、自分とまったく関係のないスポーツ関連の話で、「私のフォロワーには絶対刺さらないだろ。担当者、仕事しろ」とぼやいた記憶が……。
M:考慮すべき要素、データは膨大ですし、数字で判断できないような定性的な情報もあります。マーケティング担当者に正確に判断しろというのは酷な話ですね。特にインフルエンサー・マーケティングはグローバルなので、文化的な背景がよくわからない海外市場でのインフルエンサー探しとなると、もうお手上げです。なので、経験と直感、そして担当者の好みで選ぶ……。ということが当たり前の世界なのです。
ただ、「膨大なデータから規則性を見いだし、今後を予測する」これはAIが得意な分野です。 iKalaは台湾の通信事業者の中華電信と共同で、2600億パラメータの大規模言語モデルを開発しました。インフルエンサーが投稿したコンテンツを分析し、ライフスタイル、教育、経済、日常の話題など100以上のジャンルに分類します。また、関連コンテンツの検査も可能で、たとえば過去に「コーヒーに関する投稿はあるか」といったことも確認できます。
フォロワーについても分析し、ゾンビフォロワー、つまり金で買ったフォロワーがいないかどうかも確認します。投稿に対するリアクションなどのデータも加味し、広告クライアントが必要とする最適のインフルエンサーを探し出し、出稿費用の見積もりまで行います。
他にも細かい話ですが、インフルエンサー・マーケティングに必要な細かい機能がそろっています。たとえば、ある分野でのインフルエンサーの相関図の作成とか。ある分野で誰が一番中心なのかが可視化されます。まず、そのインフルエンサーに宣伝してもらってから、その周辺の人々に依頼するといった戦略が立案できます。
――なるほど。無名のブランドだと、インフルエンサーに広告を断られるのが悩みと聞きますが、それを回避するための戦略が練れるわけですね。「あの**さんが広告している商品なら大丈夫だろう」と引き受けてもらえるようになる、と。細かい(笑)。
広告成長のカギは「透明化」と「データ化」
――個人のクリエイターを活用するインフルエンサー・マーケティングってどうしても怪しい要素が入ってきますけど、中華電信という超大手が出資しているのもうなずけます。
M:インフルエンサー・マーケティングは成長分野ですので、今後も多くのツールが登場するでしょう。その中で、KOL Raderの筋が良いのはなぜかという点は抑えておくべきです。
AIという最新トレンドを取り入れている点が目につきますが、本当に評価すべきは「透明化」と「データ化」という、デジタル広告のキモを抑えている点だと見ています。
テレビや新聞、雑誌といったレガシーメディアの広告と比べ、デジタル広告が優位を持っていたのは広告をどのようなターゲットが見たのかというデータがあり、広告効果がかなり正確に測定できるようになった点にあります。広告価格もオークション形式などで明示されるようになりました。この「透明化」「データ化」がデジタル広告の急激な成長へとつながったのです。
デジタル広告の中では新ジャンルのインフルエンサー・マーケティングは残念ながら、そうした「透明化」「データ化」では遅れていました。この課題を解決することができれば、インフルエンサー・マーケティングの価値は大きく高まることは自明の理です。そして、AIの力によってついに壁が打ち砕かれようとしています。
データが膨大すぎる、定性的な情報が多くて処理が難しい。こうした課題から「透明化」「データ化」が遅れている分野は他にもまだまだあります。AIの力でそうした分野を変えることができれば、チャンスは大きい。こうした俯瞰的な視点を持つことも重要です。
* * *
中国には「インターネット思考」という、ビジネス用語がある。21世紀に入って大きく成長したのがインターネット産業だが、そのコンセプトを他の業界にも持ち込んで改革すればチャンスがあるというコンセプトだ。「データ化」「透明化」はインターネット思考のもっともコアな部分だろう。マットさんが言うように、さまざまな場面でインターネット時代、AI時代に合わせた変化を模索するところにチャンスはあるはずだ。
とはいえ、レガシーを変えるのはそう簡単な話ではない。というわけで、物書きの私は今もゲラに赤ペンで直しを入れている。紙とボールペンからタブレットとデジタルペンに一応進化したとはいえ、もうちょっとどうにかならないものだろうか。


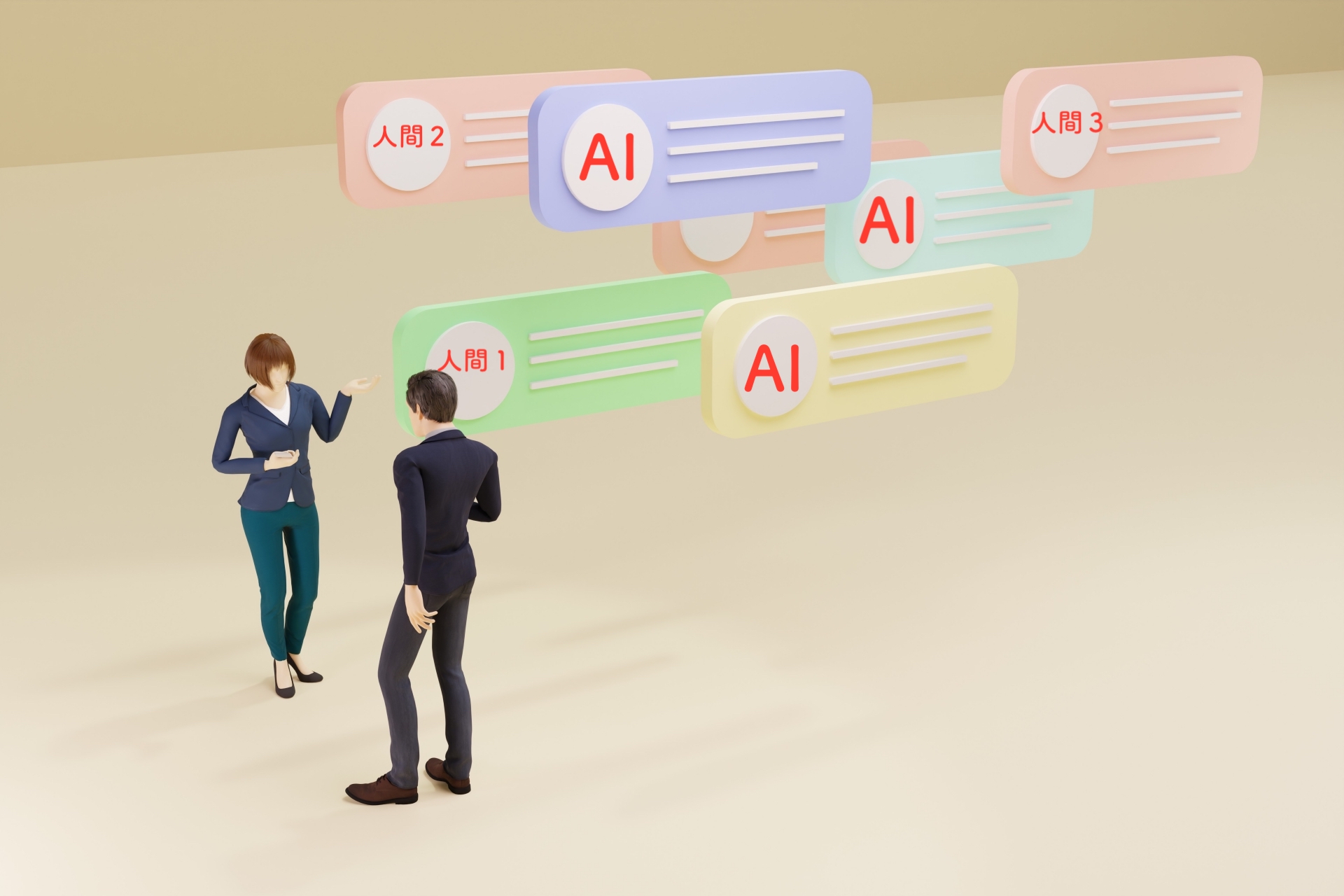









 ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり
ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり