先行する米中に追いつけるか 日本車のSDV戦略 〜第3回オートモーティブ ワールド【秋】講演より

「SDVとオープンSDV」と題した講演に登壇中の名古屋大学 未来社会創造機構モビリティ社会研究所 所長・教授の高田広章氏
モビリティ業界で注目を集めているキーワードのひとつのが「SDV(Software Defined Vehicle)」だ。これはソフトウェアによって制御される自動車のことで、購入後もソフトウェアの更新により機能や性能を高められる。すでに米国や中国では開発が進み、SDVは普及しつつある。そうした中で、日本の自動車業界はどう対応しようとしているのか。また、この先どういったSDVが登場し、どんな変革をもたらす可能性があるのだろう。
2024年9月4日〜6日、幕張メッセ(千葉県千葉市)にて「第3回オートモーティブ ワールド【秋】-クルマの先端技術展-」が開催された。その中で、名古屋大学 未来社会創造機構モビリティ社会研究所所長/教授の高田宏章氏が登壇し、「SDVとオープンSDV」と題した講演を行なった。
すでに市場投入が進む海外メーカー
SDVの定義は高田氏によると「ソフトウェアによって、機能や振る舞い、価値が定義される自動車」であり「OTA(Over The Air※)を用いたソフトウェアの追加・更新により、販売後にも、機能や振る舞いを拡張・更新できる自動車」だという。
※無線通信によって、ソフトウェアの更新を含む車両とデータの送受信をすること
「この『販売後』というのがポイントです。販売後に、無線で新しいソフトウェアをダウンロードできること。アプリも言ってもいいかもしれません、それで機能を拡張・変更できる自動車をSDVと呼ぶというのが、割と広く認められている定義です」(高田氏)
SDVのメリットとしては、まずユーザー視点として、ソフトウェア更新で機能などが追加されることで「購入後も車の価値が下がりにくくなる」ことや、アプリを追加することで「(車を)パーソナライズできる」点を挙げた。メーカー目線としては、「アプリを有料で販売したり、サブスクモデルで課金したりすることで、継続的に収益が上がる」利点を挙げた。
このようにさまざまなメリットをもたらすSDVは、すでに海外では開発が進んでおり、特に米国テスラは5年ほど前から市場に投入している。
「米国テスラが2018年にモデル3を発売した際に、消費者の立場から車を評価する『Consumer Reports』という雑誌で、ブレーキ性能が悪いとして『非推奨』とされました。しかし、その後、テスラはOTAによるソフトウェアの更新で、ブレーキ性能を向上しました。これにより『Consumer Reports』では、モデル3の評価を『推奨』に変更しました。これなどはまさに車の性能をソフトウェアで向上した事例と言えるでしょう」
「従来の自動車業界がまだまだできないぞと思っていたことを、テスラは(この時点で)もうやってしまっているわけですね」
さらに、昨年、中国で開催された「上海モーターショー2023」では、中国BYDが、ソフトウェアでいろいろな価値をつけた新しいコンセプトの車を「ある程度の完成度で出してきた」と述べ、「少なくとも自動車に関わるソフトウェアの開発速度では、(日本メーカーが)負けていることが明らかになった」と分析した。
日系メーカーの挽回策は?
では、危機感が高まる中で日本の自動車業界はどのような対応を進めているのだろう。高田氏は、その取り組みのひとつとして、国交相と経産省が進めている「モビリティDX検討会(旧『自動走行ビジネス検討会』)」を紹介した。これは、デジタル技術を活用して、新たなモビリティ産業を創出し、国際競争力の強化につなげていく官民連携の検討会で、高田氏自身が座長を務めている。
高田氏によると、モビリティDX検討会では、この5月に『モビリティDX戦略』を発表。同戦略ではまず大目標として、「SDVのグローバル販売台数における日系自動車メーカーの3割の実現(2030年および2035年の目標として)」を掲げているという。
「現在の日系自動車メーカーの世界シェアが3割ですので、これを維持するだけかと言われるかもしれませんが、今申しましたように、(米国、中国などの)新興メーカーが急速に伸び、かつ日本が弱いデジタル化が広がっている中で、この3割を維持するのは非常にチャレンジングな目標だと思います」
モビリティDX検討会では、この目標を達成するために、今後競争が生じていく3領域を「車両のSDV化」「自動運転・MaaS」「データ連携」と見定め、これらの領域における官民連携の活動を強化していくと説明した。
課題を解く鍵は“分離”にあり
「ただ、SDV化には、当然ながら課題もあります」と高田氏は日本の自動車業界が抱える課題にも言及する。技術的な課題として強調したのが、「ソフトウェアの開発工数が爆発的に増大する」問題だ。
「(日本の自動車メーカーは)車種ごとにソフトウェアを作っていますから、これが毎年、あるいは3カ月に一度バージョンアップするとなれば、車種の数だけのバージョンを作らないといけない。そのため、ソフトウェア数がものすごいことになります。これを何とかしないと、どうしようもありません」
こうした課題に対応するために、現在自動車業界では、ソフトウェアの開発スタイルに変革を起こそうとさまざまな取り組みを始めているという。そのひとつが「ソフトウェアとハードウェアの分離」だ。
「ソフトウェアの開発工数が爆発的に増大する」問題を解決するには、「ハードウェアが異なる車両を、全く同一のソフトウェアで制御すること」がベストだろう。しかし、そんなことは現時点ではまず不可能だ。そこで自動車メーカーが進めているのが「ソフトウェアとハードウェアの分離」だという。
これは、ソフトウェアの中に「ハードウェアに依存する部分(ビークルOS)」と、「ハードウェアに依存しない部分(アプリケーション)」を決め、この2つを分離して開発していくという手法だという。
「『依存する部分』は、最初から車両に組み込んでおき、頻繁にはバージョンアップしない。一方、『依存しない部分』は、どんどん新しい機能を追加する。そういう形でやれれば理想的であると考えています」
実際に、多くの自動車メーカーがこの考え方を取り入れており、例えばトヨタ自動車は「Arene OS」を、日産自動車・ルノーアライアンスは「FACE」というビークルOSを開発しているとのことだ。
「オープンSDV」で新たな市場を
もう一点、会場の注目を集めたのが「オープンSDV」という高田氏独自の考え方だ。オープンSDVとは、自動車メーカーやその委託先以外のメーカー(サードパーティ)が開発したソフトウェアを、SDVがインストールできるようになることを指す。
現状では、車に新しいアプリやサービスを載せたいと考えた会社があったとしても、自動車メーカーと交渉するという長い道のりを乗り越えないといけない。しかし、オープンSDVによって、簡単にアプリが載せられるとなると車を使った新たなサービスや価値が生み出される可能性がある。
「これは、自動車の商品性の変化につながると思います。例えば、スマホは単に電話をかける機械ではなくて、その上にいろいろなサービスを載せられる一種のプラットフォームになっている。(これと同じように)車が単に移動するための機械ではなく、いろいろなアプリを使って、新しいサービスを載せるプラットフォームになる。こういうポテンシャルを秘めている気がします」
日本の自動車メーカーは、デジタル化で出遅れた感がある。果たして、高田氏が提唱するオープンSDVを取り入れるなどし、新たなモビリティ産業を生み出していけるのかどうか。今、大きな正念場をむかえているようだ。


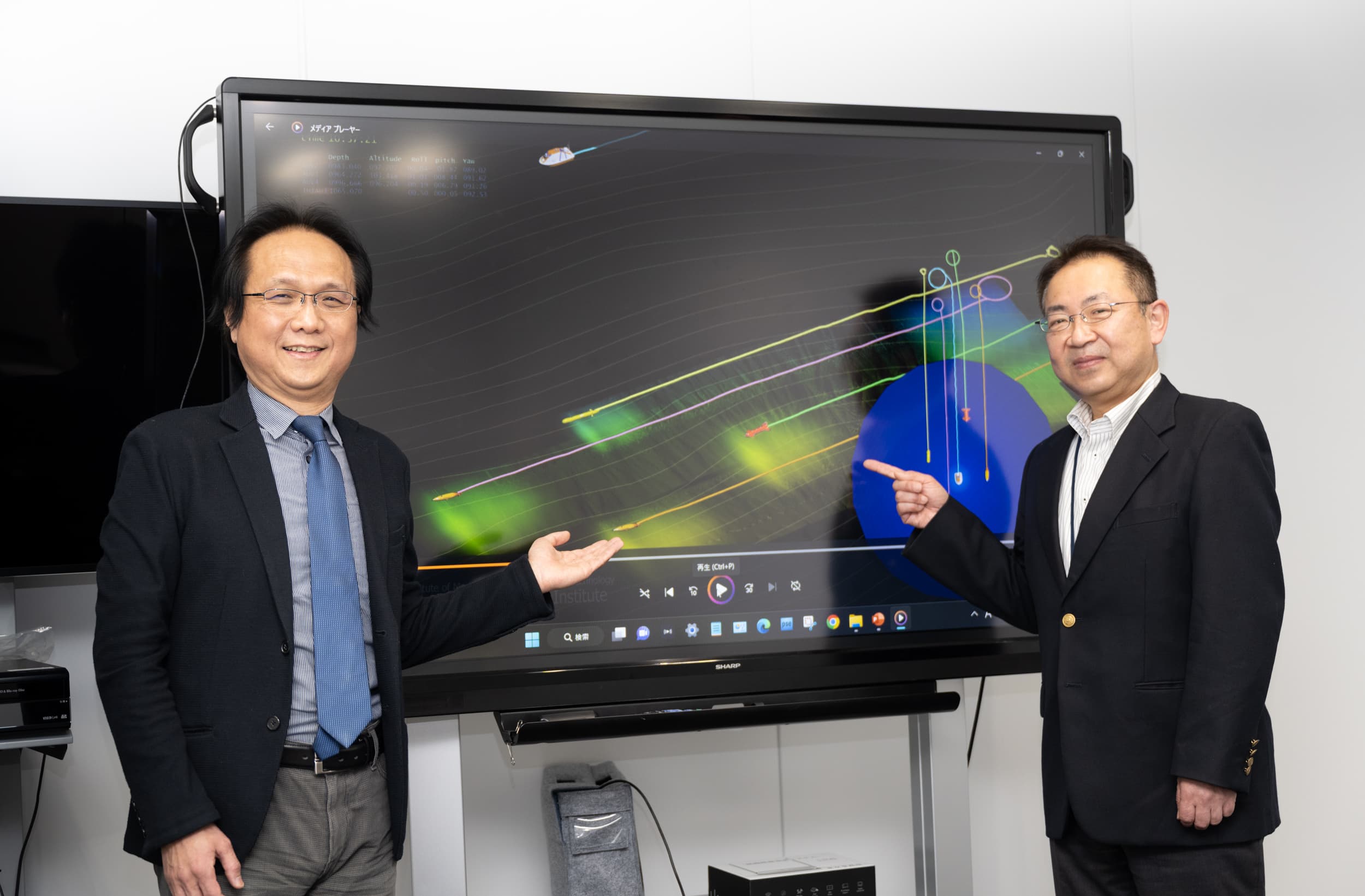








 ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり
ストックオプション(SO)は「導入」で終わらない。Boost Healthが挑む、社員の貢献を形にする継続的な文化づくり