―メディアの課題4― いまなすべきこと
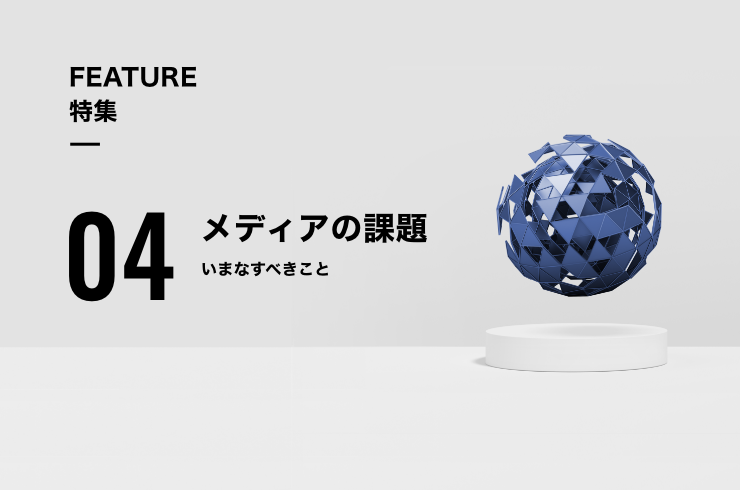
メディアの課題4 いまなすべきこと(イメージ)
出版社や新聞社などメディアの主な収入は、「販売」か「広告」の2つだと考えられてきた。
記事などのコンテンツを制作し、新聞や出版物の形にして販売し、そこに広告も入れる。紙の時代はそれだけで潤ってきたため、メディアがデジタル化した際にも、大半のメディアは、この2本柱でやっていけるだろうと考えていた。
しかし「販売」つまり課金の方は、「iモード」など一部例外はあったものの、自ら招いてしまった面もある“コンテンツ無料”の流れにあらがうことは難しい。近年、新聞社が有料化にチャレンジしてはいるが、実績は芳しくない。また、「広告」は広告単価の低下に加えて、新聞社や出版社が運営するサイトのネット上でのシェアが相対的に小さくなったため、多くの広告を受け入れ、単価の落ち込みを量でカバーすることも出来ない。
今回の取材でも、実績などの点で出版社の中では比較的うまくいっているように見える東洋経済新報社であっても「私の危機感で言うとこれがマックスなんですよ。非常にヤバイというふうに思っています」(田北氏)とのこと。では同社ではこの先どのようにこの危機を克服しようと考えているのか。
■接点を増やすことでビジネスを拡大する
東洋経済新報社は、日清戦争後の賠償金景気で日本中が沸き立つ1895年に、当時は新聞記者であった町田忠治(のち政界入りし民政党総裁)によって設立された。その創刊の辞には「健全なる経済社会は健全なる個人の発達に侍さるへからず(同社ホームページより引用仮名遣いは原文ママ)」とある。国民が賢明なる先導者になり社会を牽引できるよう、その知識と情報の源を同社が刊行物として届けるということだ。
「今でもその理念は変わっていませんので、私の理解としては、健全なる経済社会を牽引するための手段は別に問わないわけなので、今までは紙できたし、書籍だとか週刊誌だとか、データベースも早い時点でやりました。で近年はそれをデジタルでやっている」(田北氏)
このように読者との接点を次々と増やしてきたが、紙のビジネスの崩壊の速度が早すぎて、新たな接点作りが今は追いついていない。今、それを増やすべくさまざまな努力をしているという。今年7月から始めた「教育とICTのバーティカルメディア」などは、これまでの東洋経済オンライン等のマスメディアと異なり、顧客との新たな接点だ。こうした顧客との深い関係作りもこれから積極的に行っていく。関係性の深さでいえばセミナーがある。いま、年間100本ほどのセミナーを開催しているが、これも、今後さらに拡大していくという。
「デジタルだけで人々に接点が持てるというふうに思っていませんし、そこだけの収益でやっていけるというふうにも考えていません。もっといろんな接点をユーザーの方と持って、そこで収益を多面的に上げていくと。こういうことをやる必要があるなと思っています」(田北氏)
■デジタルをツールに地元住民・企業との接点を
西日本新聞社の吉村氏も同様に、コンテンツなどで顧客との接点を増やしこれをビジネスにつなげていくべきだと考えている。
西日本新聞社には「あなたの特命取材班」というコーナーがある。同社のホームページには「読者の調査依頼を受けて記者が動き、双方向のやりとりと新聞社の取材力で、疑問の解消や地域・社会の課題解決を目指します」と説明されている。ここでの試みは、読者の声をメディアに積極的に取り入れていこうというものだ。だが、読者との接点を増やす目的は記事を作るばかりでなく、より多面的なビジネスを拡大していくヒントを得るためでもある。
吉村氏によると、こうした戦略のモデルは意外なことに他の新聞社ではない。書店での店頭販売がないにもかかわらず、定期購読だけで30万部に達する50代がターゲットの女性誌『ハルメク』(株式会社ハルメク発行)のビジネスモデルがお手本だという。同誌は読者のニーズを徹底的に調査し、そこからコンテンツを作り、さらにそのデータは通販など周辺ビジネスにも活かされている。会員誌には昔からあるビジネスモデルだが、媒体に対する共感と高い信頼感、さらにデータを販売や収益拡大につなげていくマーケティングのノウハウがなければ成功しない。
新聞社には「投書」という形で届く読者の声がある。また読者以外にも展示会やイベントの開催など地元住民との接点は多い。しかしこれまではこうしたデータをマネタイズにつなげる発想はなかった。
「紙の新聞読んでないけど、西日本新聞のファンという人と、何十万人つながるか。一番そこをすべきじゃないかなって思います。」(吉村氏)
必ずしも読者である必要はない。どのくらい多くの地元住民とつながりを持てるか、そこから出てきたリクエストにいかに応え、それをビジネスにできるのか、地方に根付いた新聞社ならではの発想だ
これに加えて“デジタル”ということでは地元企業のDXのサポートを積極的にやっていく必要があると考えている。
「新聞社はまだ出来る事はあると思っています。それはコンテンツを制作する力ですよね。文章や写真だけでなく動画も作る必要があると思うのですが、長年培ってきた信頼性というものをまだ使えるうちに、新聞社がデジタルプロモーションを提案するというのがあるんじゃないかと思っています」(吉村氏)
地方の中小企業はまだ十分にデジタル化されていない。そこにビジネスチャンスはある。例えば企業サイト構築を請け負うとか、ECのサポートをするとか、人材難ならネットでの採用を手伝うなどといったことだ。実際こうした取り組みを西日本新聞社は始めている。
「なぜ新聞社がそんなことを」といった声があるのも事実だが、長年そのエリアで発行を続けている新聞社がやることなら「『そんな怪しいもんじゃないだろう』ということで、最初のドアノックはすごく早く行けます」と新聞社が手掛けるメリットはあると吉村氏はいう。
* * *
今回、「コンテンツメディアコンソーシアム」幹事社ということで、取材に応じていただいた東洋経済新報社、西日本新聞社は出版、新聞とメディアの形は異なれど、危機感のあるところと、目指す方向性については大きく異なることはなかったように思う。顧客との接点を増やすこと。それをうまくビジネスにつなげることなどだ。
それぞれの業界では両社ともにデジタル化に積極的で、その取組は単に紙のビジネスをデジタルに移し替えたものにとどまらない。イノベーションの先にあるメディア経営の形を見据え対応を進めている。
しかし、紙のビジネスの崩壊速度は加速している。危機感を持ち「コンテンツメディアコンソーシアム」に参加した28社が今後やるべきことは多い。時間はあまりない。がメディア各社の本気度が問われる。
※コンテンツメディアコンソーシアムは株式会社デジタルガレージの子会社である株式会社BI.Garageにメディア28社が出資する形で事業展開されています








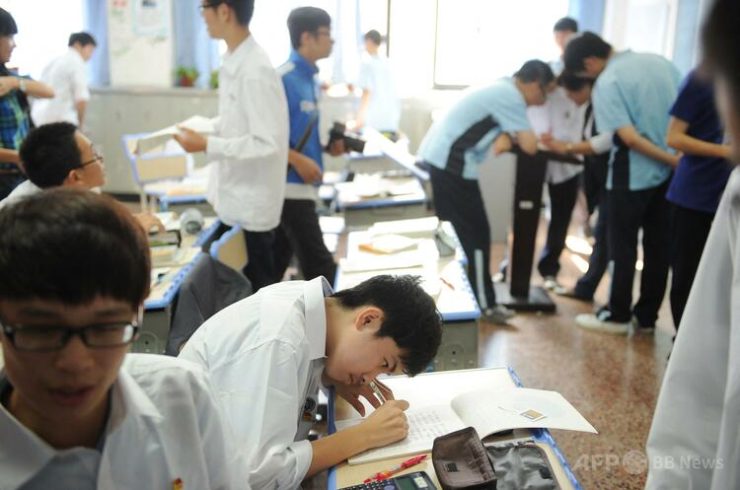


 スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs
スタートアップのM&A成功に向けて知っておくべき7つのTIPs